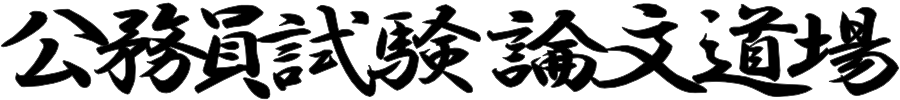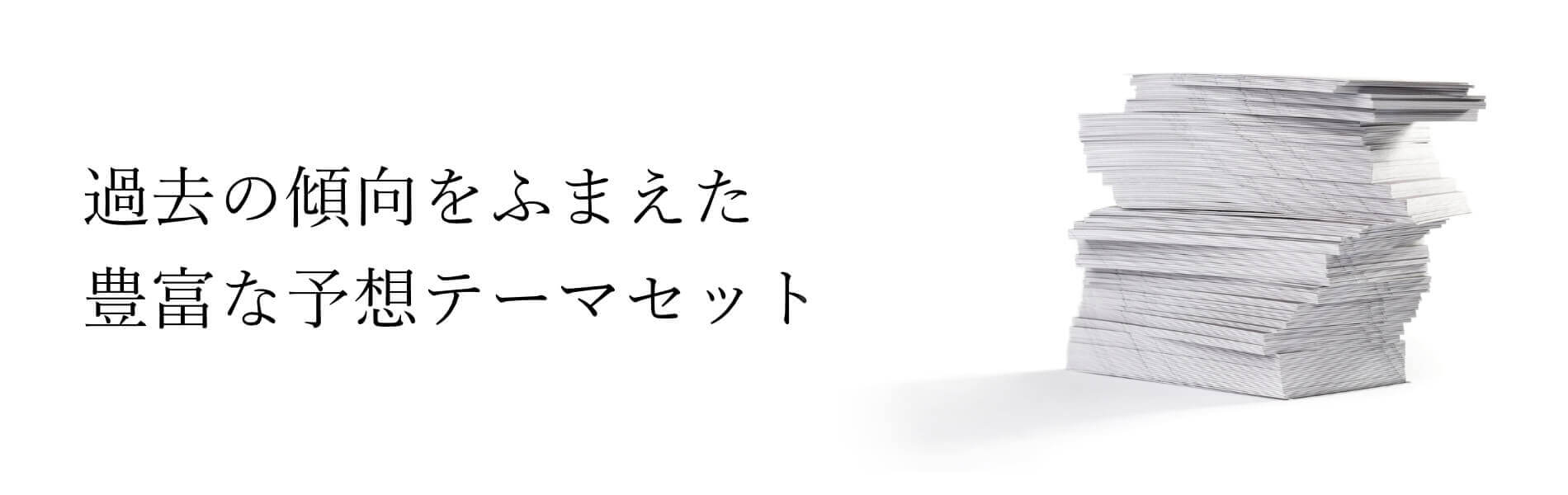公務員試験における論文テーマは非常に幅広く、対策しにくいと感じている人も多いのではないでしょうか?
たしかに各自治体の抱える問題は山ほどあり、幅広い分野から出題されるのは間違いありません。
しかし、公務員試験は繰り返し同じようなテーマが出題されることもあるため、過去問を調べることで予想を立てることは可能です。
そこで今回は、過去の論文テーマからよく出題されている頻出テーマを集計し、ランキングにしてまとめました。
具体的にどのような形で出題されるのかもイメージしやすくなるよう、実際の過去問を提示しながら紹介していくのでぜひ参考にしてみてください。
なお、論文道場では【論文予想テーマセット】を提供しています。
県庁・市役所の出題傾向を分析し、予想テーマと模範解答としてまとめたセットとなっています。
自治体別に対応しているため、あなたの志望先に特化して対策することができます。
【無料公開中!】頻出テーマの論文模範解答例
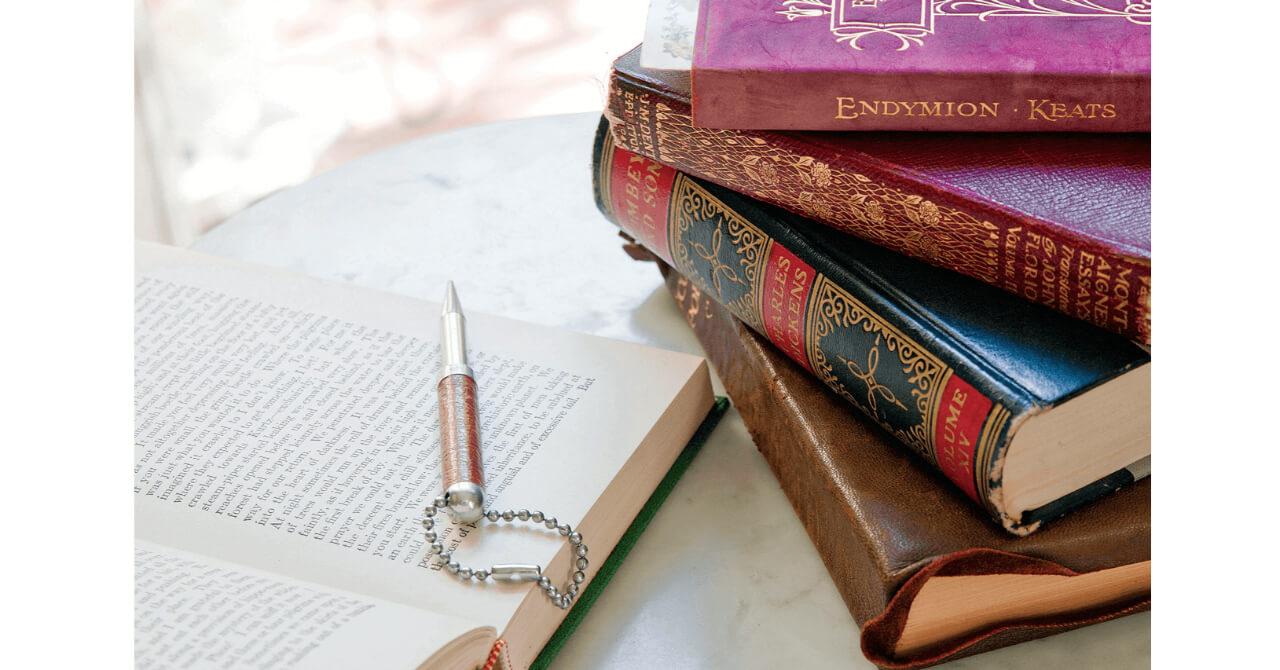
論文試験で合格するコツは、何といっても過去問を十分に勉強しておくことにあります。
そのため、まずは過去問を確認するところから始めていきましょう。
下記のページでは全国の自治体別に過去問をまとめているので、ぜひ参考にしてください。
後述するランキングにも入ってくる重要テーマのため、先に紹介しておきます。
それ以外にも、「東京都庁」「特別区」「国家一般職」「裁判所」などの主要組織の模範解答例を無料で公開中のため、これらを参考にすることでさらに論文の実力を高めていってほしいと思います。
前置きが長くなりましたが、ランキング紹介に入っていきましょう。
【最新】論文頻出テーマランキング!

今回、頻出テーマを集計するにあたっては、当サイトで収集している過去問のうち県庁・政令市・特別区で出題されたものを対象としました。
その他の市役所を受験する場合にも、基本的に県庁や政令市のテーマに準ずる形で出題されることが多いため、これから紹介するテーマを押さえておけば市役所対策としても十分です。
そして本調査の結果、頻出テーマランキングは下記のようになりました。
2位:地方創生
3位:デジタル化、アフターコロナ
4位:地域振興(地域活性化)
5位:防災・災害対策、観光振興、環境問題
【集計方法】
・大卒区分の過去問を対象(複数の大卒区分がある場合は主たる試験のみを対象)
・都道府県庁、政令市、特別区の計64自治体を調査
・過去5年間(2020~2024年)の問題、計300題以上を集計
以下にそれぞれの詳しい内容について見ていきましょう。
1位:人口減少(少子高齢化)
第1位は、人口減少(少子高齢化)関連のテーマです。
その出題回数は25回・8%と、最も高い割合を占めています。
人口減少が本番の試験ではどのような形で出題されるのか、過去問を見てみます。
福島県(2024年)
人口減少が進む中で今後課題となることを挙げ、県としてどのような取組ができるか、あなたの考えを述べなさい。
参照:<福島県庁>論文過去問
広島市(2023年)
少子高齢化や人口減少が進む中で生じる課題を一つ挙げ、その課題に対して広島市としてどのような取組を行うことが有効か、あなたの意見を述べよ。
参照:<広島市役所>論文過去問
人口減少は日本全体で取り組んでいる課題のため、必ず解答できるようにしておく必要があります。
人口減少について論じる際の書き方やポイント等については下記の記事で解説しているので、こちらを参考に対策を進めてみてください。
2位:地方創生
第2位は、地方創生関連のテーマです。
その出題回数は20回以上と、こちらも高い割合を占めています。
地方創生とは、少子高齢化の進行に対応して人口減少に歯止めをかけながら、首都圏への人口の一局集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保していくことを目指すものです。
つまり、第1位の人口減少にも関わりがあるテーマですね。
具体的なイメージが湧かない人もいると思うので、実際の過去問を見てみましょう。
岐阜県(2023年)
コロナ禍において、ICTを活用したオンラインによるコミュニケーションやテレワークが普及したことなどを機に、人々の暮らしや働き方に対する意識が大きく変化し、若い世代を中心に地方移住への関心が高まっている。こうした新たな地方分散の流れに対応し、地域の活力創出につなげていくために、岐阜県として推進すべき移住・定住促進施策について、あなたの考えを述べなさい。
参照:<岐阜県庁>論文過去問
宮城県(2020年)
令和2年に内閣官房ひと・まち・しごと創生本部事務局が行ったアンケートにおいて、東京圏在住者(20~59歳)の約50%が「地方暮らし」に関心を持っているとの結果が得られるなど、都市圏からの地方移住への関心が高まっている。そうした人たちが実際に移住するに当たって課題となりうる要素を考察し、それらの課題に対しどのような取組が有効と考えられるか、あなたの意見を述べなさい。
参照:<宮城県庁>論文過去問
地方創生のテーマは、顕著に人が減っている自治体で出題される割合が高いため、特に地方の論文試験を受ける人はしっかり対策しておくようにしましょう。
なお、地方創生について論じる際の書き方やポイント等については下記の記事で解説しているので、併せて確認しておくことをおすすめします。
3位:デジタル化、アフターコロナ
第3位は、デジタル化、アフターコロナの2テーマです。
これらは同順位で、その出題回数は各19回でした。
本番の試験ではどのような形で出題されるのか、過去問を見てみます。
大分県(2023年)
令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類へと移行し、県としても引き続き感染対策を実施しつつ、社会経済の再活性化に全力を挙げて取り組んでいるところです。今後、社会経済の再活性化を更に進めていく上でどのような課題があり、その課題解決に向けて必要な取組は何か、あなたの考えを述べなさい。
参照:<大分県庁>論文過去問
さいたま市(2021年)
さいたま市では、ICTの導入及びこれと連動する制度改正や意識改革等の包括的な実施によるデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進に取り組んでいます。アフターコロナも見据えた戦略的なDXの推進に向け、さいたま市はどのような取組をすべきか、次のキーワードから一つ選びあなたの考えを述べなさい。
「窓口オンライン化」「テレワーク」「データ活用」「業務効率化」
特別区(2024年)
デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会のために、自治体におけるデジタル・トランスフォーメーション(DX)が推進されています。こうした中で、特別区においては、専門人材の体制整備やデジタルを活用した区民サービスの更なる向上などの課題が存在しています。このような状況を踏まえ、地方行政のデジタル化について、特別区の職員としてどのように取り組むべきか、あなたの考えを論じなさい。
参照:<特別区>論文過去問
上に挙げたさいたま市は「アフターコロナ×デジタル化」という問題になっています。
このようにデジタル化は、あるテーマと組み合わせる形で出題されることも多いため注意しておきましょう。
ちなみに、コロナ関連のテーマは2020年から毎年のように様々な自治体で出題されていますが、現在は旬の話題ではなくなりつつあるため、あと数年もすれば出題頻度は下がってくると思います。
なお、デジタル化について論じる際の書き方やポイント等については下記の記事で解説しているので、併せて確認してみてください。
4位:地域振興(地域活性化)
第4位は地域振興(地域活性化)関連のテーマで、その出題回数は13回でした。
地域振興とは、文化や社会活動など地域が持つ多様な資源を活用し、地域全体の活性化や魅力を高める取組のことを指します。
地域振興について本番の試験ではどのような形で出題されるのか、過去問を見てみます。
石川県(2024年)
地域の活力を維持・向上させるための取組について
参照:<石川県庁>論文過去問
特別区(2022年)
特別区では、人口の流動化、価値観やライフスタイルの多様化によって地域コミュニティのあり方に変化が生じています。また、外国人の増加も見込まれる中、様々な人が地域社会で生活する上で、地域コミュニティの役割はますます重要となっています。こうした中、行政には、年齢や国籍を問わず、多様な人々が地域コミュニティの活動に参加できるような仕組みづくりや、既存の活動を更に推進するための取組が求められています。このような状況を踏まえ、地域コミュニティの活性化について、特別区の職員としてどのように取り組むべきか、あなたの考えを論じなさい。
参照:<特別区>論文過去問
地域を盛り上げて経済的にも文化的にも豊かになろうという考えは全国的にありますが、地域コミュニティの活性化については都市部で出題されやすい傾向にあるため注意しておきましょう。
なお、地域振興(地域活性化)の模範解答例については下記の記事で紹介しているので、どのような形で論述するのか分からない人は参考に見てみてください。
5位:防災・災害対策、観光振興、環境問題
第5位は、防災・災害対策、観光振興、環境問題の3テーマです。
これらは同順位で、その出題回数は各12回でした。
続いて、過去問を見てみましょう。
横浜市(2023年)
近年、気候変動に伴う風水害等の激甚・頻発化や、多くの被害が想定される大規模地震発生の切迫など、自然災害に対するリスクは年々高まっています。こうした状況の中でも、持続可能な都市として発展し続けるため、横浜市では災害から人命と社会経済活動を守る安全な都市の実現に向けて、地域防災力の向上など防災・減災と強靱化の取組を総合的・継続的に進めています。市民一人ひとりに「自らの命は自らで守る」防災意識の浸透を図るための取組を進めるため、横浜市職員としてどのように取り組んでいきたいか、あなたの考えを述べなさい。
参照:<横浜市役所>論文過去問
仙台市(2021年)
近年多発する自然災害に対して、防災・減災の取り組みを進めるなど、自然災害に強いまちづくりを行うために必要な行政の役割について、あなたの考えを論じなさい。
参照:<仙台市役所>論文過去問
防災・災害対策のテーマでは、地震、津波豪雨、など様々な災害に対する備えについて論じられるようにしておくようにしましょう。
また、災害に関連するテーマとして「災害復興」があります。
近年だと福島県で東日本大震災、富山県で能登半島地震への復興について出題があるため、特に被災自治体を受験する場合には”災害のその後”にも注目しておきましょう。
詳しい防災・災害対策について論じる際の書き方やポイント等については下記の記事で解説しているので、ぜひ併せて読んでみてください。
【意外と多い】自分で課題を挙げる形式の論文
先ほどのランキングでは「デジタル化」や「防災」など、「テーマとしてカウントできるもの」のみを集計しました。
しかし、実は「分かやすいテーマはないけどよく出題される形式の論文」というのも存在します。
具体例を見た方が早いので、以下の過去問をご覧ください。
千葉市(2024年)
あなたが関心のある社会問題について一つ挙げ、その内容について説明し、千葉市の職員としてどのように取り組むべきか、あなたなりの解決案を具体的に述べなさい。
参照:<千葉市役所>過去問
これを見ていただくと、分かりやすいテーマのようなものはないものの「自分で課題を挙げて解答する」という形式であることが分かります。
このような形式は県庁や市役所では頻出で、ランキングで見ると4位の地域振興のよりも多い16回となっています(この形式も含めると、実際のランキングでは4位になるということです)。
この形式はテーマを与えられるわけではないため、社会問題や課題について幅広く知識を持っておく必要があります。
自治体によっては、総合計画など計画書の中から関心のある事柄を選択して解答する形式もあります。
そのため論文対策をしていくときには、志望先の過去問を確認した上で、HPや計画書も確認しながら情報収集していくようにしましょう。
論文で必要な2つの力
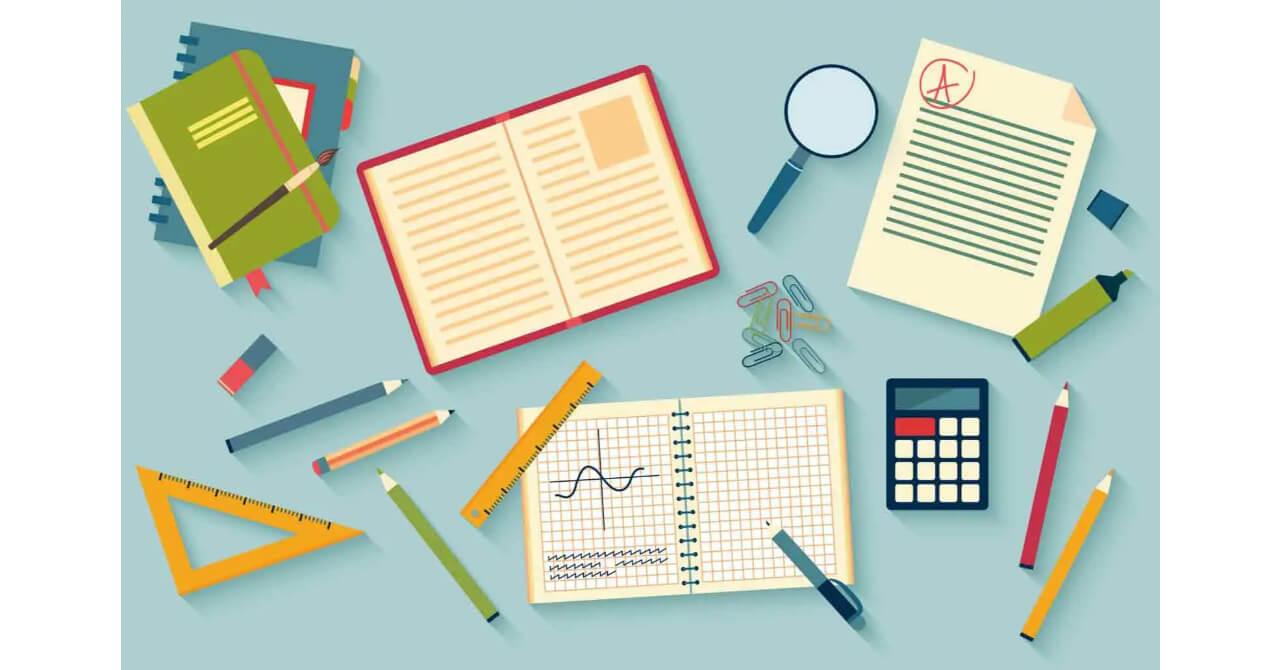
先ほど紹介したいくつかの過去問を見て分かったと思いますが、複数の自治体でテーマの被りが見られるものの、問題文や問われ方はまるで異なります。
そのため、論文においては問題を正しく読み解く力と文章を正しく作成する力の2つが求められます。
論文の勉強をする上で重要視したいのはこの2つであり、この部分ができていないと評価を上げることはできません。
例えば、以下の例題を使って具体的に考えてみましょう。
神戸市(2019年)
今後、本格的な人口減少が続く日本で、空き家の発生が加速し、地域が荒廃することが危惧されており、神戸市内においても同様の問題が発生してきています。使える空き家は「活用」・「流通」を図る一方、活用等の見通しが立たず取り残されている老朽空き家は、周辺への影響が深刻化しないうちに早期解消を図ることが必要です。空き家が地域に与える影響を分析したうえで、行政としてどのような取り組みが必要か、あなたの考えを述べなさい。
参照:<神戸市役所>論文過去問
①問題文を正しく読み解く
「問題文を正しく読み解く」というのは、簡単に言ってしまうと「読解力」のことです。
問題文をしっかりと隅々まで読み、何について問われているのかを丁寧に見ていきましょう。
先の例題の場合、空き家問題がテーマになっています。
○○問題というとネガディブなものを思い浮かべてしまいますが、例題をよく読むと、
と、空き家問題はメリットにもなり得ることが言及されています。
つまり空き家問題とはいえ、デメリット・メリットの両面を見据えた文章に仕上げないと、読解力が足りないと判断されてしまうということです。
「ああ、空き家問題ね」と冒頭部分で判断してしまうのではなく、最後まで読んでから考え出すようにしましょう。
さらに詳しい論文の書き方や文章のルールについては下記の記事で分かりやすくまとめているので、ぜひ参考にしてください。
②文章を正しく作成する
論文試験はプレゼンとは異なり、アイディア勝負ではありません。
あくまでも問題を正しく捉え、適切な回答をまとめ、文章を正しく作成することが求められています。
論述する解決策や取組については普遍的なものでも問題ないため、自分なりの意見を分かりやすく読みやすい形で書いていきましょう。
例えば例題を見ると、
と記載があります。
「行政として」と書かれているということは、その立場に即した内容を記述しなくてはいけないということです。
特に独学で対策を進めようとしている人は、これらの2つのポイントが抜けていることが多いため、この2つを意識して取り組んでいくようにしましょう。
なお、独学者に向けては下記の記事で公務員試験の論文を独学で対策する方法を紹介しているので参考にしてください。
【論文予想テーマ模範解答セット】はこちら
最後にお知らせです!
当サイトでは、論文予想テーマを集約した自治体別の模範解答セットを提供しています。
市役所などの自治体を志望する人は併願することが多いと思いますが、それぞれの自治体について予想テーマを自作するのはかなりの時間と労力を消費してしまいます。
そのため、特に論文対策を効率的に進めたい人や独学で対策に手間取っている人、試験まで時間がない人は、この予想テーマを含んだ模範解答集を利用してみてください。
この論文予想テーマセットは、各自治体の過去テーマを分析し、予想されるテーマに対する模範解答をまとめたセットです。
自治体別に対応しているため、あなたの志望先に特化して対策することができます。
模範解答集を活用すれば、テーマ研究や模範解答となる論文を書く時間を別のことに使うこともできるため、時間をお金で買うつもりで準備していくことをおすすめします。
まとめ
公務員試験の論文に取り組むにあたって、重要なのはやはり過去問と頻出テーマの把握です。
今回ランキングに挙げた頻出テーマをもとに、実際に書いて練習していきましょう。
そしてテーマを押さえたら、ステップアップした対策に入っていきます。
以下の記事では、論文の暗記のコツや論文で上位合格をする秘訣について解説しているので、併せて確認してみてください。