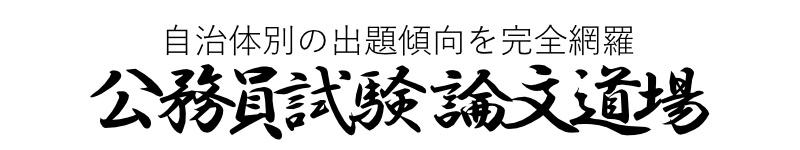神戸市役所の論文過去問と予想テーマ模範解答セットを紹介しています。
なお、下記の記事では公務員試験の論文頻出テーマをまとめています。
公務員試験受験生はぜひ参考にしてください。
試験概要
【大学卒(基礎的能力・専門試験方式)、高専・短大卒、高校卒】
・形式:論文
・試験時間:詳細不明
・文字数:詳細不明
※2024年より「大学卒(一括募集枠)(旧一般枠)」を「大学卒(基礎的能力・専門試験方式)」に、「通年募集枠Aターム(旧特別枠)」を「大学卒(適性検査方式)」に名称変更
【デザイン・クリエイティブ枠(大学卒・高専・短大卒)、障害者を対象とした職員採用選考】
・形式:論作文
・試験時間:60分
・文字数:詳細不明
※2024年より廃止
【社会人】
・形式:提案型論文
・試験時間:90分
・文字数:詳細不明
※2023年より廃止
【大学卒(適性検査方式)、就職就職氷河期世代を対象とした職員採用試験】
・形式:論文
・試験時間:60分
・文字数:詳細不明
※2024年より大学卒(適性検査方式)の論文廃止
神戸市役所の論文予想テーマ模範解答セットはこちら↓
自治体ごとの過去問の傾向や方針、全国的な出題傾向等を分析し、その傾向を踏まえた上で予想テーマ全てに模範解答を収録しました。 公務員試験の論文を知り尽くした講師が執筆した究極の対策セットをあなたに。
大学卒【適性検査方式】
総合事務
【2022年】
ハザードマップとは、自然災害により予測される災害の発生地点、被害の拡大範囲および被害程度、さらには避難経路、避難場所などの情報を地図に示したものです。神戸市においてもハザードマップを策定し、市民の冷静な判断力や行動力の向上を目指しています。しかし、約4割の人が「ハザードマップ等を見たことがない」、もしくは「見たことはあるが、避難の参考にしていない」というように、認知度は低いものとなっています。そこで、ハザードマップの認知度向上に向けた取組はどのようなものがあるか、あなたの考えを述べなさい。
【2021年】
令和3年9月にデジタル庁の新設が予定されるなど、現在デジタル改革が推進されています。神戸市では、自宅に居ながら、スマートフォンなどを使って市ホームページ上でオンライン申請や届け出ができる「デジタル市役所」の構築に乗り出すほか、市有施設のIT化やキャッシュレス化を推進しています。そこで、民間の事例も含めて、デジタル化をすればより効率的・効果的になると考えられるサービスを提示し、その理由とデジタル化の効果を述べてください。
【2020年】
「食品ロス削減推進法」が令和元年10月1日に施行されました。この法律は、国や自治体、事業者や国民一人ひとりが食品ロス削減に取り組むための責務等を明らかにしたもので、各自治体が担うべき役割の1つとして、事業者や消費者に食品ロス削減について、知識の普及や啓発活動を行うこととされています。そこで、生産、販売や消費の段階において、まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするために、神戸市ではどのような取り組みが必要か、あなたが考える具体的な対策を提案してください。
【2019年】
近年、訪日外国人数は増加しており、2020年の東京オリンピック開催に向けてさらなる増加が見込まれています。その中で、各自治体では、観光産業の振興のため、インバウンド誘致と国内外からの滞在型観光の推進を目指して、様々な施策に取り組んでいます。神戸市でも、公民連携による新たな観光コンテンツ開発や多言語サイトを利用した情報の発信等を行っています。一過性ではなく持続的に、観光客に神戸市を訪れてもらうためには、どのような取り組みが必要か、あなたが考える課題を取り上げて、その具体的な対策を提案してください。
【2018年】
わが国の人口は減少に転じ、急速な少子高齢化の進行や、ライフスタイルの大幅な変化など神戸市を取り巻く状況は著しく変わっています。行政としては、このような変化に着実に対応し、スピード感をもって政策を立案し、実行に移していくことが肝要です。特に人口減少は大きな問題ですが、人口減少に対応した都市のあり方を検討し、持続可能なまちづくりを推進することも行政の責務です。神戸市の人口が減少しており、東京一極集中が続く状況を踏まえ、神戸市はどのような点で他都市と差別化を図り、どのような都市を目指すべきでしょうか。あなたの考えを述べなさい。
【2017年】
神戸市では、市民サービスの向上や市域経済の活性化等、さまざまな行政課題の解決に向けて、民間事業者の知恵や資金、技術・ノウハウ等を活かした公民連携事業の実現に取り組んでいます。神戸市のまちづくりにおいて、民間活力の導入を通じて解決をすることが可能な行政課題の具体的な事例を挙げ、それに対するあなたの考えを述べなさい。
【2016年】
我が国では、かつて夫婦の役割は、「夫は外で働き、妻は家庭を守る」というのが一般的だと言われたことがありました。しかし、時代の変化に伴い女性の社会進出が活発となってきたことから男女共同参画社会の実現に向けて、官民を挙げて取り組むようになりました。本市でも、女性の活躍推進に取り組んでいますが、男女共同参画社会の実現について、あなたの考えを述べなさい。
【2015年】
わが国の人口が2008年をピークに減少に転じ、急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化など社会経済情勢が大きく変化する中で、今、地方創生という地方の活性化が大きな課題となっています。2014年12月に、政府により雇用創出と人口増加の好循環による地方再生の基本方針が示され、それを受けて、神戸市をはじめ全国の地方自治体は、地方人口ビジョン・地方版総合戦略プランの作成に着手しています。地方創生にあたっては、全国一律ではなく、地域の歴史や資源などを生かした、地域の自主的で自立的な取り組みが求められています。神戸市の活性化において、あなたが考える課題を取りあげて、その具体的な対策を提案してください。
大学卒【基礎的能力・専門試験方式】
総合事務
【2023年】
生物多様性は、人間社会の持続可能性の維持に欠かせないものですが、人々の経済活動による開発に伴う植物の伐採や、気候変動、外来種の侵入等で生態系バランスが壊れ、本来の豊かさが失われてしまう例も少なくありません。このうち、外来種(外来生物)の問題について、あなたの考えを述べてください。
【2022年】
人口減少社会の進展・共働き世帯の増加・児童虐待や子どもの貧困など、子育て家庭や子どもの育ちをめぐる環境が大きく変化する中で、神戸市では「神戸っ子すこやかプラン 2024」を策定しています。妊娠・出産期から学齢期において切れ目ない支援を提供することで、子どものより良い育ちの実現を目指しており、取り組む視点として以下の6つの柱を定めています。そこで、6つの柱のうち一つを取り上げ、現状どのような課題があり、その課題に対し、行政はどのような取組みを行うべきか、あなたの考えを述べてください。
①仕事と子育ての両立支援
②妊娠・出産・子育て期の支援
③特に支援が必要な子どもたち・家庭への支援
④地域における子育て支援・青少年の健全育成
⑤幼児期の教育・保育の質の向上・小学校教育との連携
⑥子育てしやすい社会環境づくりと啓発
【2021年】
神戸市では、「神戸2025ビジョン」の中で、市民一人ひとりが安心安全で心豊かに幸せを実感できる生活を享受でき、将来を担う若者が輝き、活躍できる持続可能な社会を築く「海と山が育むグローバル貢献都市」を目指すこととしており、以下の6つの基本的な考え方を示しています。そこで、6つの基本的な考え方のうち一つを取り上げ、現状どのような課題があり、その課題に対し、行政はどのような取組みを行うべきか、あなたの考えを述べてください。
〇豊かな自然と文化、多様な価値観が融合する神戸の強みを磨き、活かした新たな価値・スタイルを創造する
〇人口減少時代に向き合い、神戸のまち・くらしの質を高め、成熟都市の魅力を訴求し、好循環へ転換する
〇神戸に住み、働き、学び、楽しみ、あらゆる関係者が幸福を実感するまちを実現する
〇ダイバーシティ推進やジェンダー平等の視点を確保し、女性が活躍できる環境を整え、外国人市民をはじめとした多様な市民の参画による多文化共生社会を実現する
〇震災から再起した市民の知恵・気風を活かし、あらゆる危機への備え、誰一人として取り残さず、人を大切にする安心・安全なまちを実現する
〇テクノロジーの実装・デジタル化の加速による市民生活の豊かさと利便性向上、経済活動の回復・成長、環境貢献など、SDGsの達成による持続可能な都市を実現する
【2020年】
本格的な人口減少時代の到来、少子・高齢化の進展など、公共交通を取り巻く環境は急激に変化しています。そこで、上記のような環境の変化が公共交通に及ぼす影響を考察したうえで、公共交通が今後も「市民の足」としての役割を果たしていくためには、行政としてどのような取り組みを行うべきか、あなたの考えを述べなさい。
【2019年】
今後、本格的な人口減少が続く日本で、空き家の発生が加速し、地域が荒廃することが危惧されており、神戸市内においても同様の問題が発生してきています。使える空き家は「活用」・「流通」を図る一方、活用等の見通しが立たず取り残されている老朽空き家は、周辺への影響が深刻化しないうちに早期解消を図ることが必要です。空き家が地域に与える影響を分析したうえで、行政としてどのような取り組みが必要か、あなたの考えを述べなさい。
【2018年】
近年、大地震や集中豪雨による洪水など大規模災害が多く発生しており、災害対策や防災対策が非常に重要となってきています。神戸市においては、関係各所との連携や協力によって、災害に強いまちづくりをすすめ、大規模災害にも対応できる防災体制を確立することを目的に地域防災計画を作成しています。しかし、災害に強いまちづくりを進めるための対策事業には、多額の経費及び時間が必要となってきます。そこで、どういったものを優先的に実施することが重要か、具体的にあなたの考えを述べなさい。
【2017年】
高度経済成長期に開発が進んだ大規模ニュータウンは、戦後のまちづくりを先導し、経済成長を支える役割を果たしてきました。しかし、ニュータウンの中には、開発時に同世代の者が一斉に入居したことによる居住世代の偏りのため、高齢化と子ども世代の流出による人口減少が急激に進行しており、神戸市内にも同じ課題を抱えるニュータウンがあります。オールドニュータウンの人口減少と高齢化によって生じる問題点を検証したうえで、にぎわいのあるニュータウンに再生するためには、どのような取り組みをすればよいか、あなたの考えを述べなさい。
【2016年】
市では基本構想や基本計画を踏まえて総合計画を策定し、この目標を年次進行に応じて政策形成あるいは計画として落とし込み、実現することになります。これが行政の大切な役割です。しかし、本市のような人口が大変多い政令都市ではその住民ニーズの範囲は多様であり、対応が可能なものとそうでないものとが多数混在しているのが現状です。このような住民ニーズはどのような判断で政策に反映させるべきか、あなたの考えを具体的に述べてください。
【2015年】
商店街・小売市場は、商品・サービスの提供の機能を果たすだけでなく、地域コミュニティの核としての機能やにぎわい・文化を生み出す機能などを果たすことが期待されています。しかし、今日、顧客ニーズの変化や後継者不足、商圏人口の減少などに伴って、商店街・小売市場の衰退が神戸市も含めて全国的な課題となっています。商店街・小売市場の活性化において、あなたが考える課題を取り上げて、その具体的な対策を提案してください。
【2014年】
来年、阪神・淡路大震災から、20年の大きな節目を迎える現在、神戸市では震災経験のない住民が4割を超えています。また、震災を神戸市職員として経験していない人の割合も、全職員中の4割近くにもなっています。震災を経験していない人たちの防災意識の低下が懸念される中で、将来、発生することが想定されている南海トラフ巨大地震などの大規模災害に備えるために、阪神・淡路大震災の経験と教訓を忘れることなく地域や世代を越えて伝え続け、国内外に広く発信し続けることが求められています。阪神・淡路大震災の経験と教訓を継承・発信するためにどうすればよいのか、あなたの考えを述べなさい。
【2013年】
近年、目覚しい経済成長を続けている新興国では、人口集中に伴う各種都市インフラ整備および投資の需要が高まっています。こういった背景の中、神戸市では、新たな国際交流分野として、水循環システム・都市整備など本市が蓄積してきた経験やノウハウを活用して、地元企業等の東南アジア等への海外展開を支援する取組みを始めています。こうした公民連携の海外展開について、あなたの考えを述べなさい。
【2012年】
平成7年に発生した阪神・淡路大震外の救援活動に延べ150万人ものボランティアが全国各地から駆け付けました。その後、災害ボランティア活動が浸透していき、平成10年には社会貢献活動を促進するための「特定非営利活動促進法」が施行されました。東日本大震災でも被災者支援に、多数のNPO法人が活躍しています。その活動を支えるために、昨年、寄付を促す法改正が実現しました。被災者支援をはじめとして、NPO活動を質・量ともに拡大するためにどうすべきか、あなたの考えを述べなさい。
【2011年】
六甲山は、神戸港とともに神戸を象徴し、美しい神戸を形成している都市資源だといわれています。これまで100年以上にわたる植林緑化など六甲山を守り、市民の癒しや憩いの場としていかそうという様々な取り組みが行なわれてきました。その一方で六甲山系を総合的に管理・運営する体制が整っていません。六甲山の魅力をより向上させるために、六甲山を総合的にとらえて、保全、利用の具体的な取り組みを提案してください。
【2010年】
昨年5月16日に、新型インフルエンザの最初の国内発生が神戸市内で確認された。その前後から同6月12日までの神戸市の新型インフルエンザ対応について、危機管理の視点から検証した結果によれば、市民や企業は、神戸市が感染拡大防止のために「休校措置」「神戸まつりの中止」等を迅速に決断したことや「ひとまず安心宣言」を出して柔軟な対応をとったことを高く評価している。その一方で、国を含む行政からの十分な情報発信がなされなかったことや、感染した個人や学校への誹謗・中傷が見られたこと、マスコミの過剰報道が風評被害を招いたのではないかなどの意見が市民・企業から多く出された。このような健康危機において、情報伝達をどのようにすべきか、あなたの考えを述べなさい。
【2009年】
阪神・淡路大震災の発生から15年を迎えようとしています。被災時の地域での助け合いや復興過程での協働のまちづくりなどの経験から「人と人とのつながり(いわゆるソーシャルキャピタル)」の大切さに改めて気づきました。この震災の教訓を踏まえて、神戸市では「新たなビジョン(中期計画)」(平成17年策定)において、重要なテーマの一つとして地域での人と人とのつながりの醸成を掲げています。その一方で、我が国では人間関係そのものが希薄化していると指摘されています。地域での人と人とのつながりの醸成に向けた具体的な対策を提案してください。
【2008年】
現行の政令指定都市制度は、大都市問題に対処する「暫定的な措置」として、昭和31年9月に5大市(横浜市・名古屋市・京都市・大阪市・神戸市)を指定したことから始まったものであるが、当制度創設後、大都市制度の抜本的改革についての議論はまだ十分になされていない。しかし、大都市制度の抜本的な改革は、指定都市が、一般の市町村と共通する役割・機能を果たすとともに、大都市固有の役割・機能を十全に果たすために必要であると考えられている。指定都市が果たすべき大都市固有の役割・機能について、あなたの考え方を述べなさい。
デザイン・クリエイティブ枠(大学卒・高専・短大卒)
総合事務
【2022年】
人口減少社会の進展・共働き世帯の増加・児童虐待や子どもの貧困など、子育て家庭や子どもの育ちをめぐる環境が大きく変化する中で、神戸市では「神戸っ子すこやかプラン 2024」を策定しています。妊娠・出産期から学齢期において切れ目ない支援を提供することで、子どものより良い育ちの実現を目指しており、取り組む視点として以下の6つの柱を定めています。そこで、6つの柱のうち一つを取り上げ、現状どのような課題があり、その課題に対し、行政はどのような取組みを行うべきか、あなたの考えを述べてください。
①仕事と子育ての両立支援
②妊娠・出産・子育て期の支援
③特に支援が必要な子どもたち・家庭への支援
④地域における子育て支援・青少年の健全育成
⑤幼児期の教育・保育の質の向上・小学校教育との連携
⑥子育てしやすい社会環境づくりと啓発
※大学卒(基礎的能力・専門試験方式)と同じ問題
【2021年】
「神戸」と聞くと、ポートタワーや旧居留地、北野など異国情緒あふれる街並みから「おしゃれなまち」というイメージを思い浮かべる方が多いと言われています。また、山や海に囲まれ、自然が豊かであることや、パンや洋服など、外国からの文化を取り入れて発展してきたことも神戸市の特徴の一つです。しかしながら、神戸は多くの魅力があるがゆえに、神戸というまちを一言で表すことが難しい側面もあります。そこで、県外に住む人に対し神戸の魅力を一言で伝えるために、神戸らしさを表すキャッチコピーを一つ考え、それを使ってどのような取り組みを行うべきか、あなたの考えを述べてください。
高専・短大卒
総合事務
【2023年】
生物多様性は、人間社会の持続可能性の維持に欠かせないものですが、人々の経済活動による開発に伴う植物の伐採や、気候変動、外来種の侵入等で生態系バランスが壊れ、本来の豊かさが失われてしまう例も少なくありません。このうち、外来種(外来生物)の問題について、あなたの考えを述べてください。
※大学卒(基礎的能力・専門試験方式)と同じ問題
【2022年】
人口減少社会の進展・共働き世帯の増加・児童虐待や子どもの貧困など、子育て家庭や子どもの育ちをめぐる環境が大きく変化する中で、神戸市では「神戸っ子すこやかプラン 2024」を策定しています。妊娠・出産期から学齢期において切れ目ない支援を提供することで、子どものより良い育ちの実現を目指しており、取り組む視点として以下の6つの柱を定めています。そこで、6つの柱のうち一つを取り上げ、現状どのような課題があり、その課題に対し、行政はどのような取組みを行うべきか、あなたの考えを述べてください。
①仕事と子育ての両立支援
②妊娠・出産・子育て期の支援
③特に支援が必要な子どもたち・家庭への支援
④地域における子育て支援・青少年の健全育成
⑤幼児期の教育・保育の質の向上・小学校教育との連携
⑥子育てしやすい社会環境づくりと啓発
※大学卒(基礎的能力・専門試験方式)と同じ問題
【2021年】
神戸は開港とともに居留地が開かれ、令和3年3月末時点では過去最多の49,110人もの外国人が市内に居住しています。そのような中で、SDGs(持続可能な開発目標)においても「人や国の不平等をなくそう」が掲げられているように、多文化共生は世界的に重要な理念となっています。そこで、外国人にとっても住みやすい街であるために、神戸市はどのような政策を実施するべきか、あなたの考えを述べなさい。
高校卒
総合事務
【2023年】
市役所の仕事のほとんどは、一人で課題に取り組むものではなく、チームで協力して課題に取り組み、解決していく仕事です。チームで仕事をするにあたって必要なものがなにか、またあなたの考えとは対立する意見が出た場合には、どのように振る舞うべきか、その行動や心掛けについて、これまでの経験を踏まえ、あなたの考えを具体的に述べなさい。
【2022年】
市役所は、市民に最も身近な存在であり、色々な背景を持った市民の方が、様々な相談や手続きのために訪れます。来庁される方は、困りごとや心配ごとをお持ちの方も多く、相手の立場に寄り添った姿勢を意識することが大切です。そこで、①子育て世帯・②高齢者・③外国人の方が相談に来られた場合に、それぞれ、職員としてどのような点に留意しながら対応するべきか、あなたの考えを述べなさい。
【2021年】
神戸を若者に選ばれるまちにするために、あなたが重要だと考えるキーワードを1つとりあげ、そのキーワードを使いながら、神戸市の現状や抱える課題をふまえ、神戸市としてどのようなことに取り組むべきか、あなたの考えを述べなさい。
社会人
総合事務
【2021年】
持続可能な開発目標(SDGs)とは、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2030年までに持続可能でよりよい世界をめざす国際目標であり、17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さないことを誓っています。昨年10月には、最先端のテクノロジーを活用してSDGs上の課題解決をめざすグローバル・イノベーション・センター(GIC)が神戸に開設されるなど、神戸市では、イノベーションを通じたSDGsの実現に向けて、積極的な取り組みを進めています。そこで、17のゴールのうち一つを取り上げ、現状どのような課題があり、その課題に対し、行政はどのような取組みを行うべきか、具体策について提案してください。
1 貧困をなくそう
2 飢餓をゼロに
3 すべての人に健康と福祉を
4 質の高い教育をみんなに
5 ジェンダー平等を実現しよう
6 安全な水とトイレを世界中に
7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに
8 働きがいも経済成長も
9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう
11 住み続けられるまちづくりを
12 つくる責任 つかう責任
13 気候変動に具体的な対策を
14 海の豊かさを守ろう
15 陸の豊かさも守ろう
16 平和と公正をすべての人に
17 パートナーシップで目標を達成しよう
【2020年】
「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」(内閣府)によると、テレワークの経験者のおよそ4人に1人が地方移住への関心を高めていることが分かりました。また、東京都23区に住む20歳代についても、地方移住への関心は高くなっています(約35%)。東京一極集中が進行するなか、若年層を中心に神戸への移住を推進するために、神戸市として、今後どのような取り組みに注力していくべきか、具体策について提案してください。
【2019年】
人口減少が進行するなか、子どもの健やかな育ちや子育てにおける親の不安・負担の解消・軽減等のため、妊娠・出産から子育ての各ライフステージに応じた支援の充実が求められています。喫緊の課題である人口減少対策として、子どもの成長に応じた切れ目のない施策を展開し、誰もが「安心して子育てができる街」を実現するため、神戸市は行政としてどのような取り組みができるか、あなたの考えを提案してください。
【2018年】
神戸市では、現在、コミュニティづくりや地域交通の未来、アナログ業務の効率化、シティプロモーション等の分野において、本市の地域・行政課題をスタートアップ(成長型起業家)・ベンチャー企業と市職員が協働して解決する国内自治体初の取り組みであるプロジェクトを始めています。これらの分野に限らず、民間事業者と行政の協働により解決されうる行政課題と解決のための具体策について、あなたの考えを述べなさい。
【2017年】
近年、団塊世代の退職、少子化による労働力人口の減少などにより、職種を問わず様々な組織において、多くの優秀な人材を採用することが難しくなっています。そこで、あなたが働きたいと感じることができる組織の要素とその理由を3つあげ、中でも最も大切だと考える要素を組織に浸透させるための具体的な取り組みを提案してください。
【2016年】
少子高齢化の進行により、わが国の生産年齢人口は1995年をピークに減少に転じており、総人口も2008年をピークに減少に転じています。本市においても、この少子高齢化の進展に伴い社会保障経費が確実に増大することが見込まれるとともに、生産年齢人口の減少に伴い、本市の歳入の基幹となる市税収入は減少することが予想されます。この人口減少社会を克服し、まちを安定した成長軌道に乗せていくためには、新たな財源確保が必要となってきます。そこで、本市の歳入(収入)を増加させていくための施策としてどういったことが考えられますか。あなたの考えを述べなさい。
【2015年】
少子化の進む日本において、経済発展の手段とし外国人観光客数等を増やす「観光立国」が脚光を浴びています。国は、訪日外国人旅行(インバウンド)者の増加を目的としたビジット・ジャパン・キャンペーンを展開しています。神戸市においても、「観光交流都市」の実現を目指し、積極的に外客誘致プロモーションや受入体制の整備等に取り組んでいます。その結果、神戸市内を訪れる外国人観光客数(推計)は、平成22年に57.7万人、平成26年には約75万人と増加傾向にあります。神戸市の外国人観光客の更なる誘致促進に向けて、ハード面やソフト面での具体策を提案してください。
【2014年】
各地方自治体では、将来の人口減少、人口構成の高齢化、厳しい財政状況など地域を取り巻く環境、住民ニーズが大きく変化する中、これまで自治体が単独で取り組んできた分野に、民間の知恵やアイデア、資金や技術、ノウハウを取り入れるためのしくみや体制の構築が進められています。神戸市においても、平成25年度に、民間事業者からの提案・相談を広く受け付けるワンストップ窓口として公民連携推進室を開設し、様々な行政課題の解決に向けて、民間事業者が主体となった取り組みを推進しています。効果的・効率的な公民連携を進めるためにはどうすればよいのか、あなたの考えを述べなさい。
【2013年】
社会経済のグローバル化の進展によって、様々な分野で国境を越えた相互依存関係が深まり、自治体にも地域の特性を活かした独自の国際協力が求められています。神戸市では、米国・シアトル市や韓国・仁川広域市など8か国8都市と「姉妹・友好都市」提携を、また米国フィラデルフィア市や韓国・大邱市と交流分野を特定した「親善協力都市」提携を結んでいます。さらに、本年、ベトナム・キエンザン省と、上水道・下水道分野における技術協力・交流に関する覚書を締結しました。海外諸都市との人・経済・技術などの多面的な協力を推進することは都市政策上どのような意義を持ち、また、どのような具体的な推進策を講じるべきかについて、あなたの考えを述べてください。
【2012年】
各自治体は、21世紀のリーディング産業として期待されている観光の振興を通じて、地域の活性化や新しい地域文化の創造に取り組んでいます。神戸市も、海や山などの自然や異人館、温泉、田園、などとといった多種多様な観光資源を生かしながら、観光交流を推進しています。今後、神戸のリーディング産業としての役割を果たせるよう、観光振興に向けて、ハード面やソフト面でどのような具体策を講じるべきか、あなたの考えを述べてください。
【2011年】
阪神・淡路大震災からの復興過程において、文化・芸術は、多くのものを失った人々の心を癒し、神戸市民の生きる力を与えてくれました。また、近年、文化・芸術の持つ「創造性」を高めることによって、市民の創造力を引き出し、都市の活性化につなげていくことが目指されています。そこで、文化・芸術を活かし、市民の生活を豊かにするとともに、まちの賑わいや活力を生み出す具体的な対策を提案してください。
【2010年】
神戸では、阪神・淡路大震災の教訓の一つとして、地域での人と人のつながりが復興を進めていく上で重要であるということを学びました。また、近年、全国では、経済・社会環境や人々の意識の変化により地域のきずなが希薄化している反面、人々のつながりが生活満足度を高めると言われています。そこで、地域でのつながりの構築に向けた具体的な対策を提案してください。
就職氷河期世代を対象とした職員採用試験
総合事務
【2023年】
神戸のような成熟都市では、これまで市民、民間企業、行政がつくり上げてきたものが必然的に古くなり、老朽化していきます。たとえば、昭和30年代以降の人口増加に対応するため整備された計画的開発団地は、まちびらきのタイミングで同じ世代が一斉に入居したことから、入居世代が偏っており、人口減少・高齢化が進行することで、空き家・空き地の増加、生活利便施設の撤退、施設の老朽化など、さまざまなオールドタウン化の問題が顕在化しつつあります。 そこで、このような住宅団地を再生し良好な住環境を維持するため、また、都市の高質化のために、どのような施策を行っていくべきかについて、あなたの考えを述べてください。
【2022年】
今日、生産年齢人口の減少や、介護・育児をしながら働く人の増加、ワークライフバランスを重視する人の増加などの環境変化を受け、持続可能な未来に向けて、多様な働き方で誰もが活躍できる「働き方改革」が求められています。限られた財源や人員の中で、行政サービスを低下させることなく、「働き方改革」を推進していく上で必要なことを、推進にあたり生じうる課題点に触れながら述べてください。
【2021年】
新型コロナウイルス感染症拡大により、人との接触機会が制約されたことで、「孤独・孤立」の問題に社会的関心が大きく寄せられています。このため神戸市では、令和3年4月、こども家庭局に担当局長を新設するとともに、福祉局・健康局・こども家庭局の3局で構成するプロジェクトチームを設置し、総合的・効果的な対策の推進に向けて全庁的に取り組んでいます。そこで、「孤独・孤立」の問題が発生する背景を考え、問題解決のために取り組むべきだと考える政策について、具体的に述べてください。
障害者を対象とした職員採用選考
総合事務(大学卒)
【2023年】
神戸市には23もの大学・短期大学があり、約7万人の学生が集っています。 国内の政令指定都市のなかでも大学数は3位、市の人口のうち学生が占める割合も3位と、全国有数の大学都市、「大学都市KOBE」です。一方で、若者の転出者数が多いという課題も抱えています。 そのため神戸市では、学生と地域(地元企業、各種団体等)との交流を通じ、学生自身の成長と市内定住の促進に取り組んでいます。 そこで、あなた自身の学生時代の経験等を踏まえ、どうすれば学生と地域との交流が促進できるか、あなたの考えを述べてください。
【2022年】
現在、神戸市では、市民に市政情報を伝えるために、広報紙の発行のほか、ホームページや、フェイスブック・ツイッターなど、様々な媒体を使って広報を行っていますが、情報が必要な市民に必要な情報が届かないなど改善すべき事項も多く抱えています。そこで、市政情報をより効果的に広報するためには、どのような取り組みをすればよいか、あなたの考えを述べなさい。
【2021年】
神戸市では、「スマート自治体」の実現という中長期的な目指す姿と今後5年間の行政運営及び財政運営の方向性を示した「行財政改革方針2025」を策定しました。本方針に掲げる「スマート自治体」とは、市民が「いつでも、どこでも、早く、簡単に」行政サービスを利用できるようにするとともに、より重要性が高まってくる相談業務を充実させるなど、将来に渡って市民サービスの維持・向上を目指すものです。そこで、あなたが考える行政手続きスマート化するべき手続きを一つ挙げ、その必要性と効果に触れながら提案してください。
※行政手続きスマート化
電子申請のほか、Webサイトを通じた郵送申請の支援や、申請内容の事前登録など窓口滞在時間を短くする新時代の窓口申請の仕組みを構築すること
総合事務(高専・短大、高校卒)
【2023年】
神戸市に在住する外国人の数は2014年頃から増加傾向にあり、2023年7月現在で5万2,945人となっています。 神戸市では、国際都市としての魅力をさらに高めるため、外国人が住みやすく働きやすい環境を整備したり、日本語学習を希望するすべての在住外国人に対し、ニーズに応じた日本語学習環境を提供したりするなど、在住外国人との共生の推進に取り組んでいますが、神戸市民と在住外国人の交流をさらに深めていくためにはどのようなことができるか、あなたの考えを具体的に述べなさい。
【2022年】
昨今、新型コロナウイルス感染症の影響や、働き方改革の一環として、様々な組織で、在宅勤務、モバイルワーク、サテライトオフィス等のテレワークが導入されています。テレワークを導入した場合のメリットとデメリットを挙げた上で、導入にあたり、職場により大きな効果を生み出すためにはどうしたらよいか、あなたの考えを述べなさい。
【2021年】
行政による市民向け広報活動では、行政から発信される情報は市民がほしい情報や興味関心がある情報とマッチしていない、広報の効果を測定できていない、計画的で戦略的な広報ができていないなどの課題が指摘されることがあります。こうした課題も踏まえつつ、SNS(※)全盛の時代、どのように行政の広報に取り組むべきか、あなたの考えを述べなさい。
※ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略で、登録された利用者同士が交流できるWebサイトの会員制サービスのこと。
【神戸市役所】論文予想テーマ模範解答セット
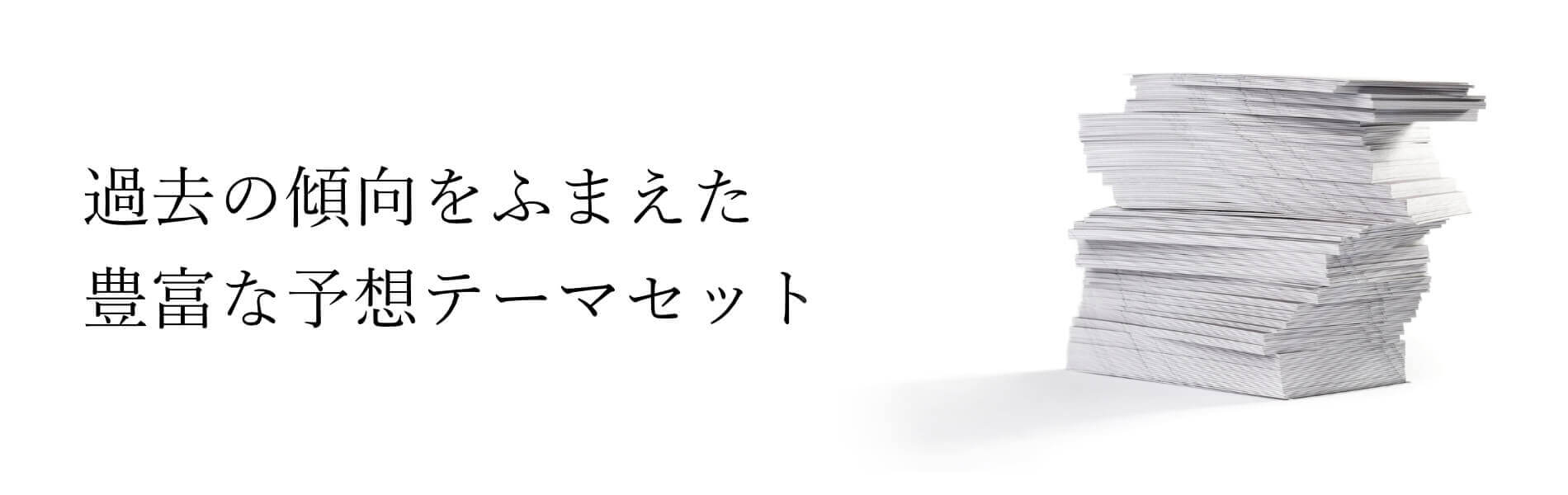
これまでの神戸市役所の過去問を徹底分析し、出題傾向を完全網羅しています。
また、総合基本計画である「マスタープラン」において示されている「めざす都市像」を解析し、出題可能性が高い予想テーマについても内容に組み込んでいます。
その上で、全ての予想テーマについて模範解答を作成した、充実のセットとなっております。