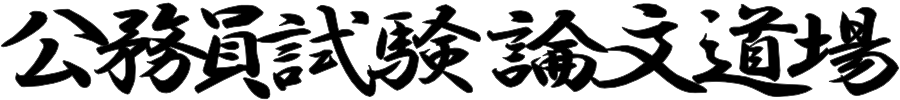公務員試験では、多くの場合に論文試験が行われます。
ひたすら暗記すればある程度得点できる教養試験と違って、論文試験は対策が難しいと感じている受験生も多いことでしょう。
公務員の論文試験では頻出テーマがいくつかあるので、それについてしっかり対策をしておくと非常に書きやすくなります。
中でも今回は、頻出テーマの一つである「防災(災害)対策」を取り上げて解説します。
防災・災害についてはどの自治体においても課題とされている重要なテーマなので、必ずチェックしておきましょう。
合格者答案も模範解答として載せているので、今まさに公務員試験対策をしている方にとって非常に参考になると思います。
「防災対策」をテーマにするにあたり、押さえておくべきコツは主に次の3点です。
・ハード面・ソフト面の両方を押さえる
・構成の「型」を押さえる
それぞれ詳しくご紹介していきます。
あわせて、下記の記事では公務員試験の論文頻出テーマをまとめたものを紹介しているので、まだ読んでいない人はこちらも読んでみてください。
防災対策で押さえるべきポイント
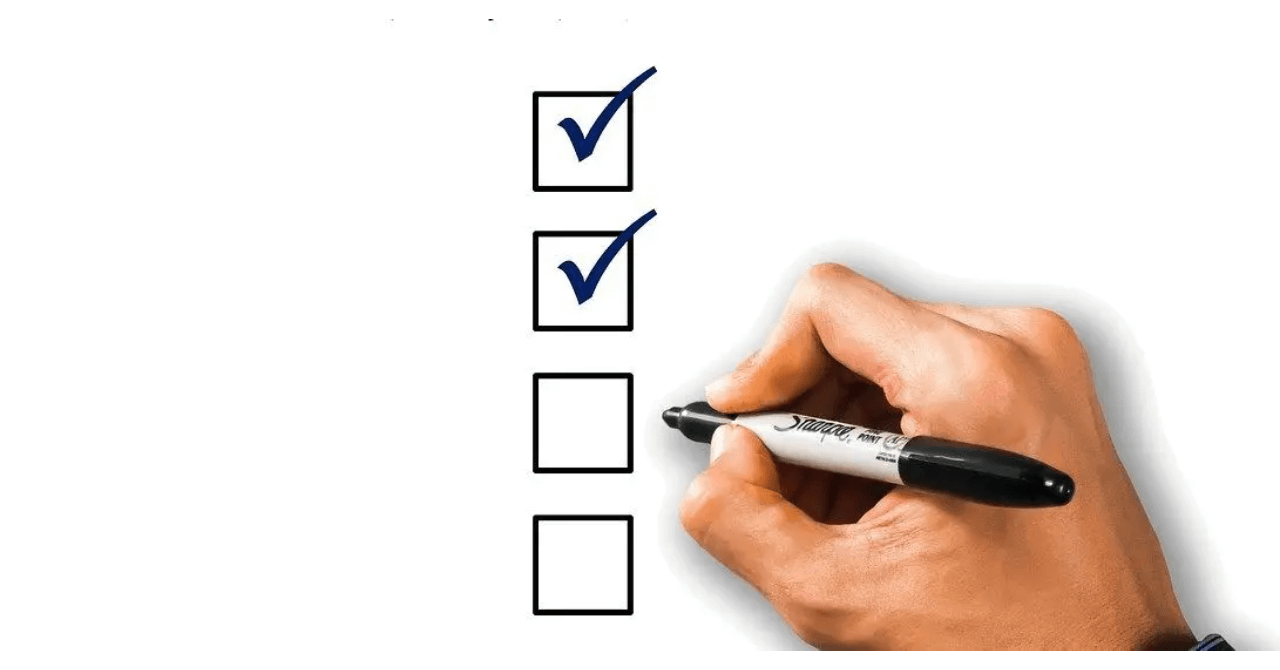
防災対策で押さえるべきポイントはたくさんありますが、今回は公務員試験の論文対策で特に必要な視点を2つ紹介します。
ポイント①災害状況の理解
防災対策を論じるためには、前提として、近年日本各地で発生した災害についての知識が欠かせません。
特に東日本大震災や能登半島地震をはじめとするような地震災害への対応を問う問題は頻出テーマとなっています。
また、毎年のように起きている集中豪雨や台風による風水害、地域によっては火山噴火による降灰等の被害や豪雪による被害も発生しているので、これも注意が必要です。
このような過去の災害について、原因や被害状況、実施された対策や対応とその課題などを一通り調べておきましょう。
受験する自治体で発生した災害は特にチェックが必要です。
ポイント②ハード面の整備
行政が行う重要な取組としては、まずはハード面が挙げられます。
ハード面は防災体制の充実や、そのための助成金制度の充実などの法整備、また災害発生の際の対応マニュアルの策定などがあります。
受験する自治体の情報に日頃から目を通し、どのような対策がなされているかを頭に入れておきましょう。
またハザード・マップ(防災地図)等も確認し、避難場所や避難経路などの情報や問題点を整理しておきます。
調査したことはノートに整理して、繰り返し目を通せるようにしておきましょう。
【自治体では特に重要】ソフト面も要チェック
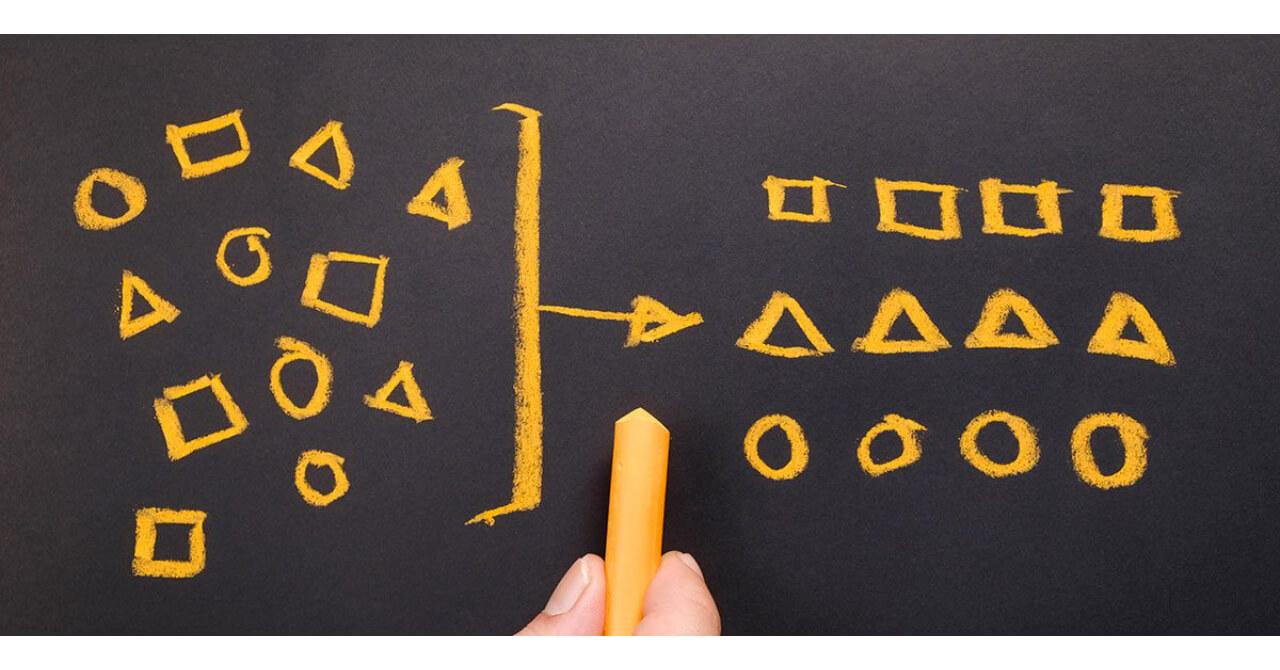
防災対策のハード面を確認したら、次にソフト面も要チェックです。
論文対策が不十分な受験生は、このソフト面についての論述が不十分なことが多いように思います。
差がつくところなので、しっかり押さえておきましょう。
ソフト面がハード面と異なるのは、住民が大きく関わる点です。
災害時には行政だけですべてに対応することは難しく、住民一人ひとりが日頃から適切な判断力と行動力を身につけておくことが求められます。
そのために必要な対策について知っておくことが重要で、特に覚えておきたいのは自助・共助という概念です。
特に近年は行政が行う「公助」だけに頼らず、住民一人ひとりが自分や家族単位で備える「自助」、互いのスキルやアイディアを持ち寄って助け合う「共助」の体制の構築が求められています。
防災訓練への地域ぐるみの積極的な参加やハザードマップの確認はもちろん、日頃から地域の催しなどを通して住民同士のコミュニケーションを図っておくことが非常に重要です。
論文ではこの点を必ず盛り込んでいきましょう。
【具体例で紹介】構成の「型」を押さえよう!

過去の災害を確認し、ハード面とソフト面の対策を押さえたら、いよいよ実際に書く練習に入りましょう。
論文が苦手な人はいきなり書き出してはいけません。
まずは論文構成の「型」をしっかり頭に入れましょう。
①問われたことについての自分の意見
②現状分析とその問題点
③解決策や取組
④解決策や取組の根拠
⑤結論
続いて仙台市の過去問を例に、この型をどう使うか具体的に見ていきます。
【2021年】
近年多発する自然災害に対して、防災・減災の取り組みを進めるなど、自然災害に強いまちづくりを行うために必要な行政の役割について、あなたの考えを論じなさい。<仙台市役所>論文過去問を参照
・仙台市として防災対策を進めるうえで重視すべきは、「自助・共助・公助」の考え方にもとづいた対策立案である。
・仙台市では、ハード面の防災対策としてすでに〇〇、〇〇などが行われているが、それだけでは十分とは言えない。過去の災害(東日本大震災など)を見ても、非常時には行政など公的機関の「公助」が行き渡るまでに時間がかかることが多い。
・「自助・共助」の住民コミュニティを構築する。住民一人ひとりの防災意識を日頃から高め、災害時に「公助」が行き渡るまでのセーフティーネットとして、住民がそれぞれのアイデアやスキルを持ち寄って助け合える関係をつくることで、ソフト面の強化をしていく。
・ハード面をどのように強化しても、住民の自主的な備えや、緊急時の的確な判断・行動が伴わなければ被害を押さえることは難しい。逆に、東日本大震災の際の「釜石の奇跡」のように、住民が日ごろから防災教育や防災訓練を通して学び、災害時には声を掛け合って最適な行動をとることで、自分たちの命を守ることが可能となる。
①で述べた自分の考えを、②~④を踏まえて結論として再提示する。
いかがでしょうか。
上記の①~⑤の構成の型は、基本的にどのようなタイプの論文にも応用することができます。
また、設問文の中に「あなたの能力・経験をどのように活かせるのか」などの文言があった場合は、「③解決策や取組」の部分には、「自分ならこういう経験・能力を活かしてこのように取り組む」という“自己のスキルアピール”をさらっと入れましょう。
今回の仙台市の過去問のように自己PRを直接的には求めていない場合、それをくどくどと書くのは逆効果になるので注意が必要ですが、課されたテーマの流れの中での自然なアピールは可能な範囲で入れておきたいところです。
【合格者答案】論文模範解答例

ここで、参考までに合格者の論文模範解答を掲載しておきます。
全文を読み、「こういう風に書けばいいんだ」という感覚を掴んでみてください。
【防災対策】模範解答例
日本では近い将来、南海トラフ地震の発生が予想されている。また、日本の自然災害の発生数は年々増加しており、SDGs達成目標にも「気候変動による災害に備えた対策」や「災害に強いまちづくり」が掲げられている。防災対策においては、建物の耐震性を強化するなどハード面を重要視することも大切だが、地域や個人レベルでの備えなどソフト面の対策も十分に行わなければならない。以下、自然災害から○○県民の命を守り、身体面や経済面での被害をなるべく小さく抑えるために、防災対策において今後求められることを3点述べたい。
第1に、個人や家族単位での行動や防災意識向上を促すことである。災害への危機意識は慣れにより、年々風化していく傾向がある。そこで行政は、防災意識向上の取組を継続的に行うことが求められる。具体的には、学校や家庭における防災学習を促し、習得した知識を実際に使えるように、居住する地域の状況に応じて実地訓練を行う。また、災害時の避難場所やハザードマップの確認、避難持ち出し袋の点検を徹底させるため、ホームページやパンフレットを積極的に活用して日常的な発信を続け、防災意識を強く持てるよう浸透させていく。これらの行政の取組によって、個人や家庭における自助力を高めていく。
第2に、緊急時の行政側の対応には限界があるため、自主防災組織として地域住民が協力し助け合うことが必要である。その主な活動としては、避難誘導訓練、防災マップの更新、災害時の役割の確認などがある。実際に災害が起こった場合には、初期消火、要救助者の確認、救助活動や避難誘導を行うことになる。しかし、自主防災組織が存在したとしても、それが認知されておらず、活動自体も有形無実化しているなど課題も山積している。そこで、行政が地域コミュニティと連携し活動を強化することで、地域の共助力を強化していくことが大切だ。
第3に、もちろん住民や地域への働きかけだけでなく、行政自体の対応力を上げることが必要だ。その際は、複合災害にも柔軟に対応できるような備えが重要である。たとえば、コロナウィルス感染防止と災害避難とを両立させる場合を検討する。その際は、事前に地域の宿泊施設と連携して「分散型避難」の態勢を整えておく。さらに住民に対しては車中泊や知人宅避難など、工夫のある避難方法を知ってもらう。加えて、公共避難所のレイアウトの見直しや消毒薬、マスクなどの物資の準備も欠かせない。このように複合的な災害に応じて備えることが、公助力の強化に資すると考える。
以上のように、自然災害から住民の命と暮らしを守るために、ハード、ソフトの両面から計画的に準備を進めるべきである。私は、住民の災害への危機意識向上に努めつつ、行政職員として緊張感を持って防災対策に取り組む覚悟である。
【特別区専用】論文模範解答例を無料公開!
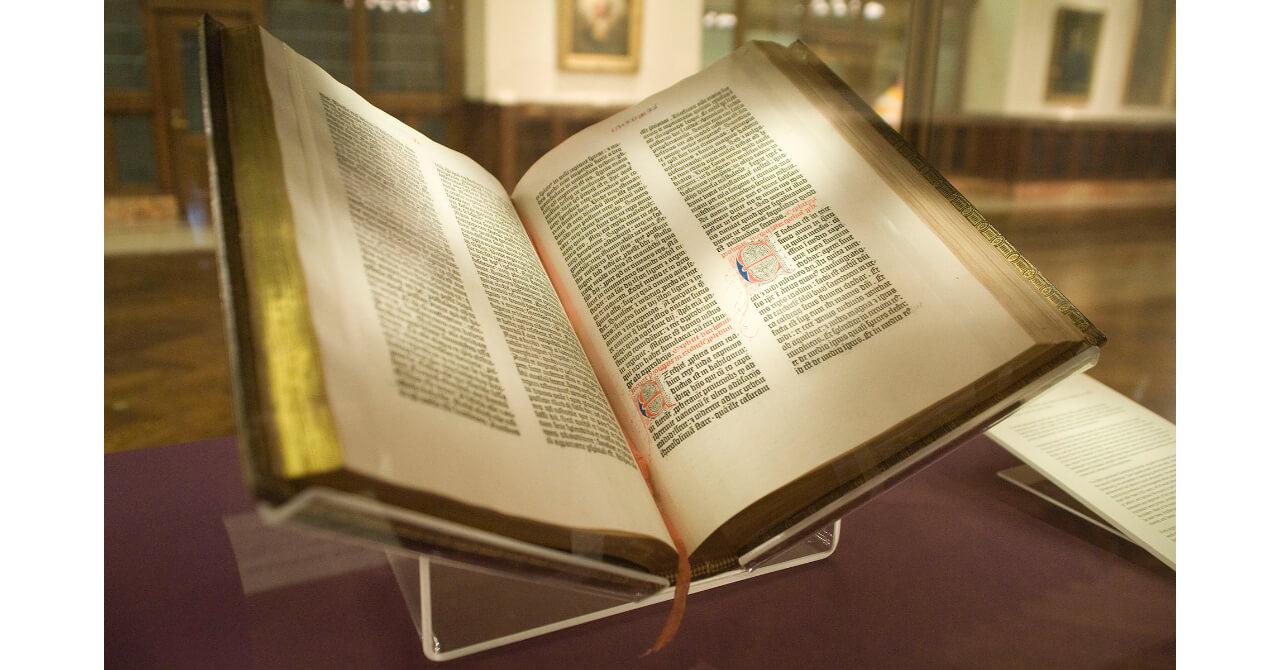
防災対策はどの自治体でも出題可能性が高い頻出テーマですが、特に論文の重要性が高い特別区においてもやはり過去に出題があります。
そこで受験生の皆さんに参考にしていただくために、下記の記事では公務員試験論文道場で指導を受けた特別区Ⅰ類合格者の模範解答例を無料公開しています。
テーマ別に掲載しており、防災対策(危機管理)についても公開中です。
特別区を受験しない人でも十分、論文対策の参考になるので一読して損はありません。
【裁判所専用】論文模範解答例を無料公開!

防災対策は国家公務員試験の頻出のテーマとしても知られており、裁判所での出題が確認されています。
そこで受験生の皆さんに参考にしていただくために、下記の記事では公務員試験論文道場で指導を受けた裁判所一般職合格者の模範回答例を無料公開しています。
テーマ別に掲載しており自然災害対策についても公開中ですが、裁判所を受験しない人でも参考になること間違いなしです。
まとめ
今回は、公務員試験の論文の頻出テーマである「防災対策」について解説しました。
「防災対策」を論じるにあたっては、行政のみで行うハード面の施策だけでなく、日頃から住民を巻き込んでの「自助・共助」を育てるコミュニティづくりの重要性に触れることが大切です。
官民が協働して防災・減災に取り組むというあり方ですね。
それを説得力を持って論じるために、受験する自治体の最新情報を収集し、しっかりとノートに整理しておきましょう。
あとは、ご紹介した構成の「型」を使って書く練習を積み重ねましょう。
書いたら書きっぱなしにせず、必ず信頼できる人の添削を受け、繰り返し書き直してよりよいものにしていくことが必須です。
今回お伝えしたことに沿って練習を繰り返せば、論文試験も怖くありません。
努力を積み重ねて、合格を勝ち取りましょう。
なお、下記の記事では全国の公務員試験の論文過去問をまとめています。
公務員試験受験生は参考にしてみてください。