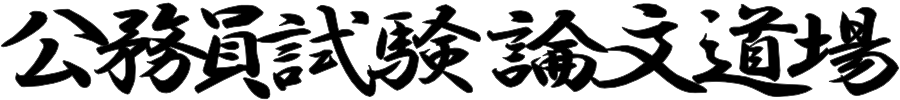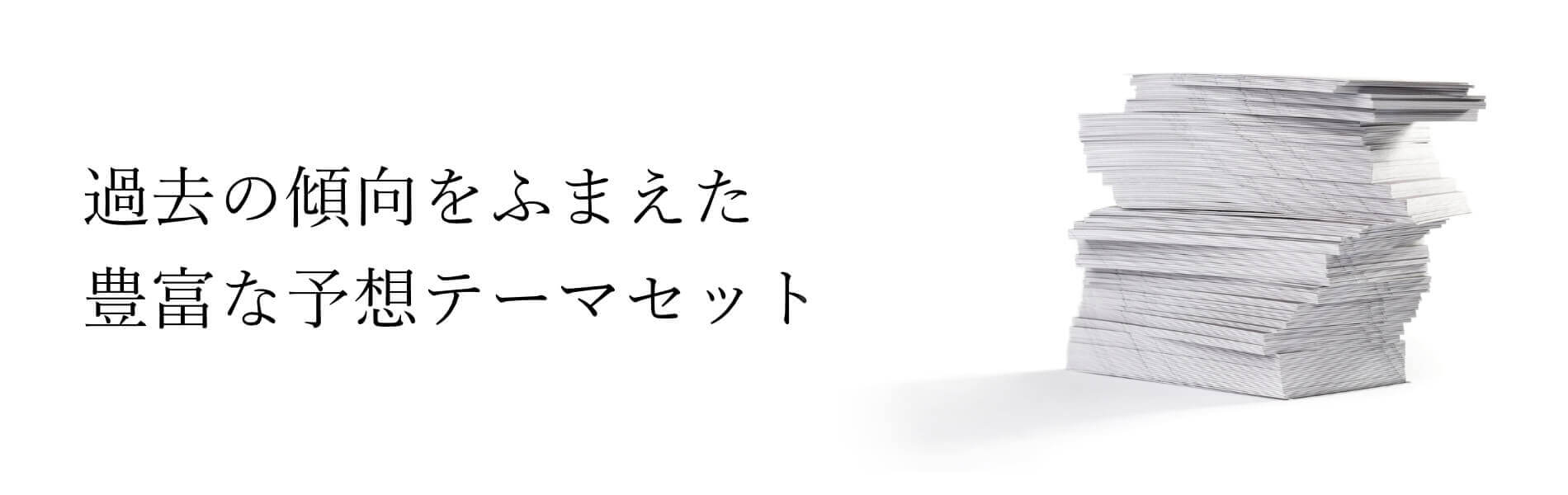一昔前と比べると論文試験に特化した教材が増え、インターネット上などでも公務員試験対策のノウハウを得やすくなりました。
また論文は日本語で書きますし、全く聞いたことのないようなテーマが出題されるわけでもないため「勉強しなくてもなんとかなる」と思う人も少なくありません。
しかし、実際には対策をせずに合格できる人は希少です。
学校の試験のように「とりあえず必要な文字数は書いているからギリギリ合格点を取れる」ということは、公務員試験にはないのです。
そう言われると、
・高校や大学で論文を書いたことはあるが、まともに作成できなかった…
などと不安を抱く人もいるかもしれませんが、公務員試験の論文は「ある程度の暗記」と「練習」によって点を取ることができるのが救いでもあります。
そこで今回は、これから試験を控えている受験生に向けて論文対策を効率的に対策する方法を紹介していきます。
特に本記事を見ている人の多くが独学の受験生だと思いますので、独学の人に向けた対策方法を中心に解説します。
本当に必要な暗記と適切な練習をしないと時間を無駄にしてしまうので、ぜひ論文対策を進める上での参考にしてください。
本記事で分かることは次の通りです。
・論文対策を始める時期
・論文で意識すべきこと
ちなみに、下記の記事では公務員試験の論文頻出テーマをまとめています。
全国の市役所・県庁の出題傾向を徹底的に分析しているので、ぜひ併せて読んでみてください。
論文を独学で対策をするときのポイント
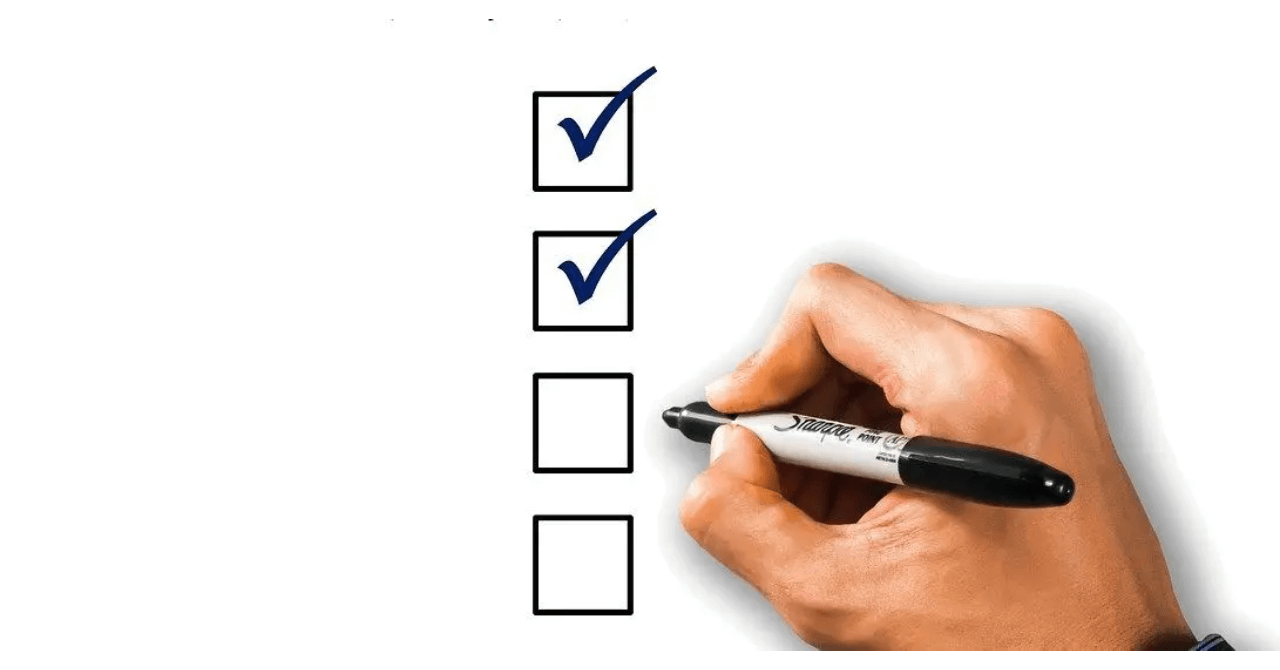
それでは早速、独学で論文試験の勉強を効率よく進めていくための4つのポイントについて紹介していきます。
①論文の「型」を身につける
論文対策においては、まず「型」というものを理解しないことには始まりません。
論文の型に決まったものはなく人によって異なりますが、一般的なものとしては次のようなものがあります。
②本論(問題の解決策と根拠)
③結論
まずは序論のところで課題や問題点について触れ、次に本論でその課題をどう解決していくのかを具体的に述べ、最後に結論で締めます。
この型に合わせて論述するだけで、全体としてまとまりのある、論理展開の分かりやすい論文を書くことができます。
それだけではなく、型を身につけておけば論文の作成が速くなるというメリットもあります。
受験先によっては論文試験の時間制限が厳しいところもあるため、早く作成できるようにしておくに越したことはありません。
また論文(作文も含む)では、こうした型と合わせて原稿用紙の使い方や文章の基本的なルールも満たしていなければなりません。
例えば句読点は1マス使うなど、いわゆる小学校で習うような文章の基本ですね。
実は論文ではこうした文章のルールや誤字脱字など細かいの部分も当たり前のように見られているため、ルールを破った論文はそれだけで減点される可能性が高いです。
そのようなことにならないよう、文章の基本的な書き方についても論文対策の一環として事前に確認しておくようにしましょう。
具体的な論文の書き方や文章のルールについては下記の記事で分かりやすくまとめているので、ぜひ参考にしてください。
②頻出テーマを押さえる
論文対策をする上では、論文で出やすいテーマに関しても知識をつけておく必要があります。
これは予備校等を使うにせよ独学でいくにせよ必要なことではありますが、独学だとどのテーマが出やすいのかを自分で調べなければならないという点に難しさがあると思います。
さらに頻出テーマは国家公務員や地方公務員、市役所や区役所など組織によって変わってくるため、自分の受験先が過去にどのようなテーマを出題しているのかを調べておく必要があるというのもあります。
しかし他の科目の勉強もある中で、論文過去問のテーマ調査だけに時間を使うのも難しくキリがありません。
そこで論文道場では、独学の皆さんに向けて公務員試験の論文頻出テーマと組織ごとの過去問をまとめています。下記のリンクからチェックしてみてください。
この頻出テーマで紹介しているものについて、一例を抜粋しました。
災害大国日本。災害に対する具体的な解決策を提示できるようにしておきましょう。
公務員試験の論文テーマとしてよく扱われています。「公務員」試験ですから「世界単位で環境問題をどうするか」ではなく、「公務員として環境問題をどうするか」という視点を持つことが大事です(これはこのテーマに限りません)。
日本が直面している大きな課題として、公務員試験の論文で非常に出やすいテーマです。
デジタル化のメリット・デメリットを理解し、社会や自治体が抱える問題を見つけ出し、解決策を提示できるようにしましょう。
「地域コミュニティの弱体化しているが、それをどうすればいいか」という方向性の出題がされやすいです。
ニュースなどで目にする機会も多いでしょう。他のテーマとも結びつきやすい話題です。
日本の労働人口の減少などに関連させて出題される場合が多いです。
日本の空き家率は年々増加しています。
これらの頻出テーマの背景や取組について理解し、得点源となる論文を書けるようにしていきましょう。
③模範解答を読み込む(暗記する)
論文の型を身につけ頻出テーマを押さえたら、ここからは実際に論文を書いてみるわけですが、その前にもう一つやることがあります。
それは、模範解答(模範答案)を読み込むことです。
いきなり論文を書くのは難しいもので(特に初心者の人なら尚更)、やはり見本のようなものを一度見てみないことには論文の勉強は始まりません。
どのような完成形に持っていけばよいのか、まずはイメージをつけるためにも模範解答を確認していきましょう。
模範解答を読み込んでいくと、先ほど紹介したような論文の型やテーマに関する知識をインプットすることができ、非常に対策が立てやすくなります。
【補足】どの程度読み込めばいいのか?
ここでは「読み込む」という表現を使いましたが、実際には自分で書き写してみて、ある程度暗記してしまうという方法がおすすめです。
そうすれば本番の論文試験の出題を見たときに、「模範解答Aのあの部分と、模範解答Bのあの部分を組み合わせればいい」という形で、自然と論文を書く道筋が見えるようになっていきます。
論文と聞くと「ゼロから自力で考えて文章を生み出すこと」が理想と思えるかもしれませんが、実際には暗記科目に近い要素もあるということを理解しておくと、後の対策がとても楽になります。
【無料公開中!】模範解答を入手する方法
模範解答を活用した勉強方法をする場合、良質な模範解答を使っていく必要がありますが、インターネット上に出回っている模範解答の中には質の低いものも散見されるため注意が必要です。
また、自力で模範解答を作るという方法もないわけではありませんが、多大な時間と労力がかかりますし、やはり「本当に適切な模範解答になっているのか」を自分で判断するのは困難なためおすすめはできません。
そこで論文道場では、公務員試験講師が執筆した模範論文を無料公開しています。
下記の記事では公務員試験の論文模範回答例を多数紹介しているので、論文対策にぜひ活用してください。
あわせて、論文予想テーマを集約した自治体別の模範解答セットも提供しているので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。
④実際に書く・添削を受ける
模範解答を何パターン暗記したとしても、実際に書くトレーニングをしないと本番でスムーズに論文を作成することはできません。
そのため、ある程度インプットができたらアウトプットに移行し、書く練習をしていきます。
そして、書いたら書きっぱなしにするのではなく、書き上げた論文は第三者に添削してもらいます。
添削で合格点以上がもらえたら力がついてる証拠なので、そのまま同じように他のテーマについても同様の対策を進めていきましょう。
「完全独学でやりたいんですけど…」と思った人もいるかもしれませんが、唯一この「添削」については独学(自分一人)で達成するのが難しい部分になります。
論文はその性質上、どうしても自分で点数をつけることはできません。
予備校の添削サービスや模試、学生であればキャリアセンターを活用するなど、添削だけは必ず専門機関に依頼をして実力を測るようにしましょう。
論文対策はいつから始めるべきか?

論文の勉強は、難易度が高い試験なら半年くらい前から、比較的難易度が低い試験なら2~3か月前くらいにはスタートするのがおすすめです。
この点については、下記の記事でより詳しく解説しているので、論文対策をこれから始める人はこちらの記事も併せてご一読ください。
論文を早めに始めるべき人は、例えば次のような人です。
・論文の配点比率が高い自治体を受ける人
・テーマによって完成度にバラつきがある人
・前年受験したものの論文で大きなミスをした人
このような人の場合には、半年くらい前から始めるべきだと思います。
論文対策の参考書などの中には「1週間でマスター」「2週間で対策できる」などと書かれているものがありますが、これはある程度実力がある人にしかできない荒業です。
特に論文試験を受けるのが初めての人や論文に苦手意識を持っている人、倍率や難易度がそこそこある試験等の場合にはおすすめできないやり方なので注意しましょう。
論文で意識すべきこと
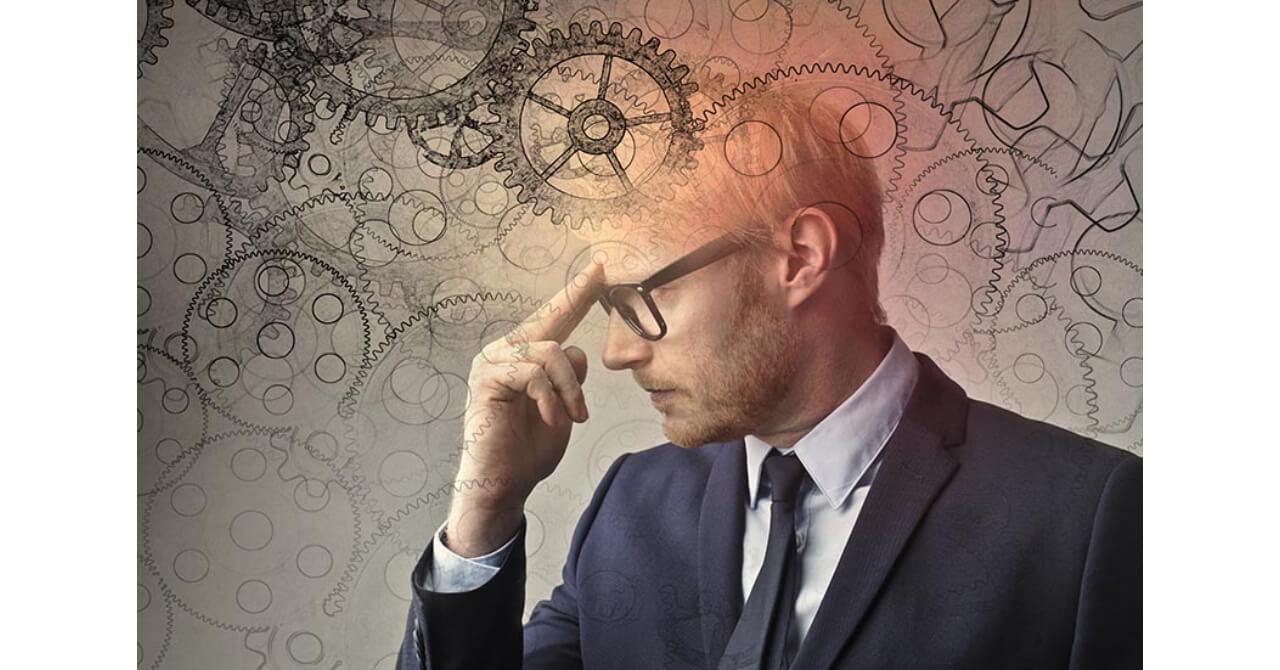
最後に、独学で論文対策を進める上で「ここはぜひ意識してほしい」というポイントを2つ紹介します。
①論理的で分かりやすい文章を書く
公務員試験の論文は研究機関などの専門的な論文ではないため、受験生レベルで深遠な知識が求められることはありません。
このことから、知識のインプットばかりに時間をかけすぎるのは非効率になってしまいます。
論文試験で最も重要なことは論理的で分かりやすい文章を書くことであるため、書く練習を積み重ねてアウトプットに時間をかけることを意識するようにしましょう。
例えば、読み手が以下のような感想を抱く論文は「論理的でなく分かりにくい」という評価になってしまいます。
・それらしい結論を出しているものの、根拠が見えない
・「結論」も「根拠」も出しているものの、なぜそれらが結びつくのかが不明瞭である
・2つの意味に取ることができる部分があり、どちらを主張したいのか判別できない
適切な論文の型で展開していけばこのような失敗はしにくいため、型を意識した論理展開をできるようにしていくのがポイントです。
②速く丁寧に書けるようにしておく
意外と大切なのが、丁寧な字で書くことです。
ものすごく綺麗な字である必要はありませんが、とめ・はね・はらいを意識した丁寧な字を書くことは意識すべきです。
字が汚いとそれだけで印象が悪くなりますし、殴り書きのような字になっていれば、最悪採点者が読めずに大幅減点や足切りをされる可能性もあります。
また論文試験の制限時間は決して長くはないため、速く(+丁寧に)書くトレーニングが必須です。
「そんなことは練習しなくてもできる」と感じるかもしれませんが、現代はパソコンやスマートフォンが主流のため、字を書く機会が極端に少なくなっています。
そのような人がいざ字を書いてみると、「力が入らず字がヨレる」「簡単な漢字を思い出せない(読めるのに書けない)」などといったことが発生しがちです。
実際にたった今、字を書いてみてはいかがでしょうか。
「あれ、書けない!」と感じたのであれば要注意です。
決して油断せず、普段の勉強のときから意識して速く丁寧に書く練習をしていきましょう。
まとめ
今回は、独学で公務員試験の論文対策をする方法について解説しました。
解説したことをまとめると下記の通りです。
・頻出テーマをインプットする
・模範解答を読み込む
・自分で書いて添削を受ける
・論理的で分かりやすい文章を書く
・速く丁寧に書く練習をする
これらを地道に行っていけば、独学でも合格点に達することは可能です。
ぜひ本記事を参考に、論文試験を突破していきましょう。
ちなみに、下記の記事では公務員試験の論文模範解答例を多数紹介しているので、ぜひ併せて参考にしてください。