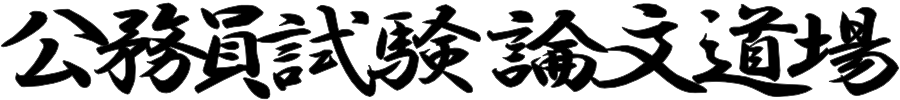突然ですが、公務員試験の論文には足切り(ボーダーライン)があることを皆さんはご存知でしょうか?
足切りとは、一定の基準に満たない論文と判断された時点で即不合格となってしまうことを指します。
例えば択一試験で高得点が取れていても、論文の内容次第では不合格になってしまうこともあるため、受験生の皆さんは足切りにならないよう十分に気をつけなくてはいけません。
こんなことを言うと不安を煽っているように感じるかもしれませんが、受験者数が多ければ多いほど足切りを設定されている場合が多いのは事実です。
今回は、足切りになる論文とは一体どういった論文のことなのか、また足切りにならない論文を書くためにはどうすれば良いのか、対策方法を詳しく紹介していきます。
本記事で分かることは次の通りです。
・足切りはどのくらい発生するか
・足切りになる論文の特徴
しっかりと対策をしていれば足切りに引っかかることはないため、ぜひ本記事を参考に対策を進めてみてください。
ちなみに、下記の記事では公務員試験の論文頻出テーマをまとめています。
全国の市役所・県庁の出題傾向を徹底的に分析しているので、ぜひ併せて読んでみてください。
論文で足切りになる人はどのくらいいる?
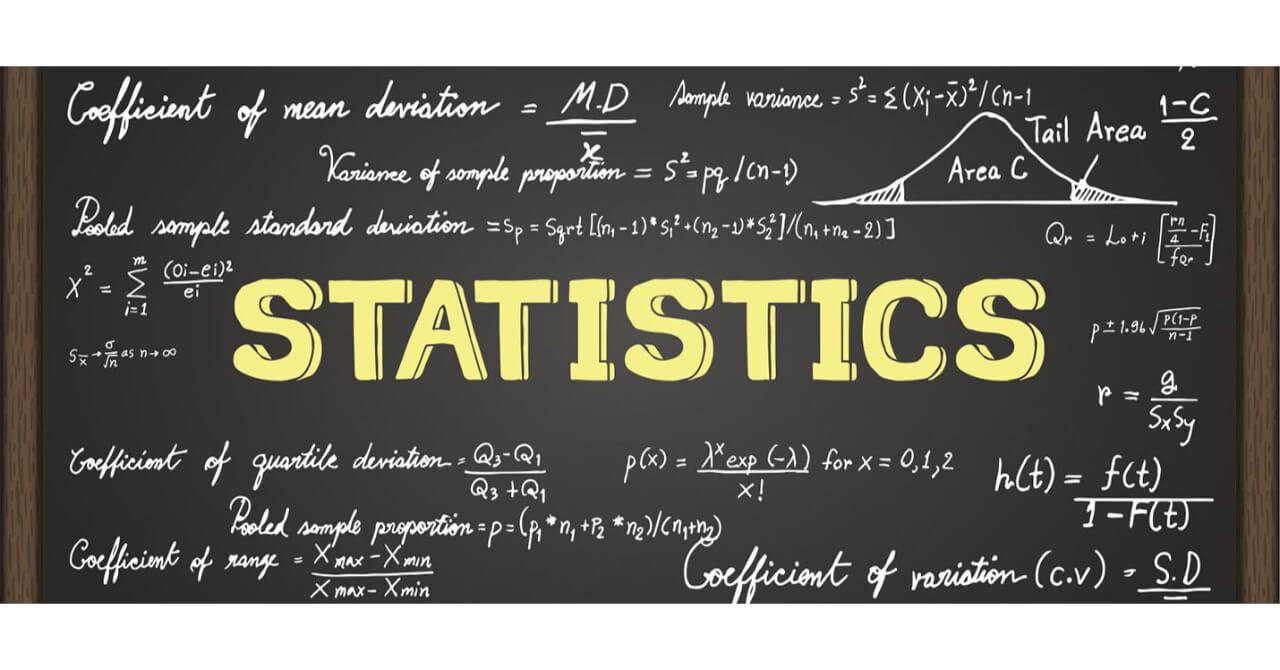
まずは足切りになる人がどのくらいいるのか、実際の数値を見てみましょう。
実は、論文の足切りが推測できるようなデータを公表している組織はほとんどないのですが、国家一般職が平均点や基準点などを公表しているので、これを使用して計算します。
これまでの国家一般職のデータをもとに算出してみると、足切りとなった受験生は全体の4~5%程度いることが分かりました。
つまり100人受験生がいるとすると、そのうち4,5人は足切りラインに引っかかっている計算です。
ちなみに、国家一般職の論文試験は1~6までの6段階で評価されます。
4段階:約45%
3段階:約45%
2段階以下:約5%(足切り)
9割の人は6段階中3~4段階の評価となり、それ以外の10%の人が高得点か足切りかに二分されるということです。
※ちなみに、国家一般職の論文過去問をご覧になりたい方は、下記の関連記事から確認いただけます。
これは国家一般職の例ですが、その他の多くの組織においても同程度の割合となっている可能性があります。
多いか?少ないか?で言うと、そこまで多くはないということですね。
すなわち、論文として正しく成立しているものであれば足切りに引っかかることはないため、過度に心配する必要はありません。
ただしほとんど論文の勉強をせずにいると、他の受験生に差をつけられて足切りになってしまう可能性もあるため、平均以上の論文は書けるようにしておく必要があるということは強調しておきたいと思います。
足切りになる論文の特徴
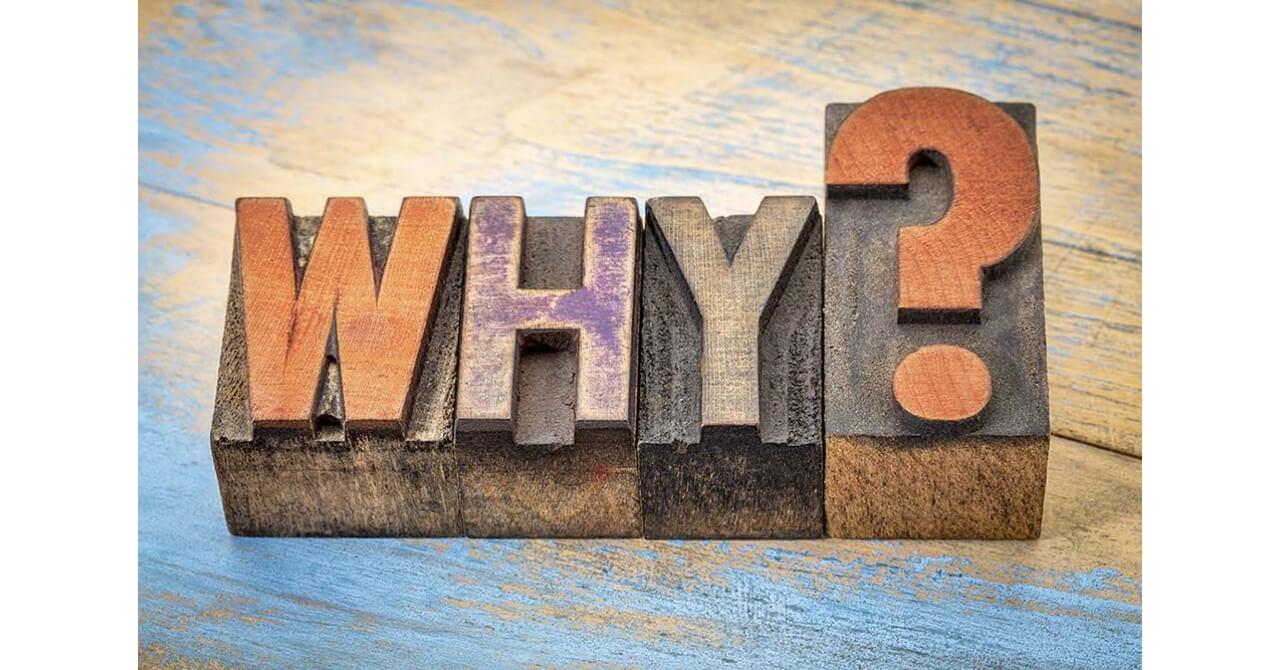
では、具体的にどのような論文だと足切りになってしまうのか?特に多い4つの原因を紹介します。
①名前や受験番号の書き忘れ
まず名前や受験番号を書き忘れると、足切りの対象となってしまう可能性大です。
「いやいや、名前と受験番号はさすがに書き忘れないでしょ?」と思うかもしれませんが、緊張などの理由でこのミスをしてしまう受験生が毎年必ず発生します。
特に論文試験は、教養試験や専門試験といった択一試験を終えた後に行われることが多いため、疲れのあまり集中力が欠如してか、書き忘れてしまうことがあるようです。
このようなミスをしないためにも、試験開始と同時に必ず「名前」や「受験番号」を先に書くようにしてください。
自宅で論文の練習をする際にも、名前や受験番号を書く癖をつけておくと安心です。
②字数が少なすぎ・多すぎる
字数制限はそれぞれの試験によって異なりますが、論文だと800~1500字くらいが一般的で、このうち8割以上は埋めたいところです。
7割未満だと絶対ダメというわけではありませんが、確証を持ちたいならやはり8割以上です。
そのため、普段から8~9割を目指して練習しておくことを推奨します。
例えば1000字の指定がある場合には、最低でも800字は書きましょう。
加えて、字数がオーバーしてしまうことも足切りの対象となり得る点には注意しておきましょう。
③誤字脱字が多すぎる
近年はスマートフォンの普及により、漢字を読めるけど書けない人や正しい文章の形が分からない人が増えています。
これが論文に顕著に出てしまい、誤字や脱字が散見されるケースが非常に多いのです。
公務員の仕事は民間の仕事以上に文書を使用することが多い職業のため、特に誤字脱字には十分に気をつけて書くようにしましょう。
論文だからといって、あえて難しい漢字や言葉を選ぶ必要はないため、自分の書ける範囲で間違いなく伝わる文章を書き上げるのがポイントです。
また論文試験には制限時間もあり、見直しをしている余裕があまりない可能性もあります。
仮に見直しをして誤字脱字が発覚しても、字数の問題などで書き直している時間がとれないこともあるため、とにかく正確に書くことを意識しましょう。
④正しく解答できていない
「問題文をしっかり読むこと」は論文試験を受ける上でとても重要なことですが、意外とできていない受験生が多いものです。
端的に言うと、適当に読んで分かったつもりになっている人が多いんですね。
「ちゃんと毎回読んでるから、私は大丈夫!」「絶対できている!」と自信のある方ほど注意が必要です。
よくあるのが、問題文のうち解答すべき内容に全て答えられていないパターンです。
例えば、
という問題があるとします。
この問題には、解答すべき内容が3つあるのがお分かりいただけるでしょうか?
このような問題文で「対策」と「活かしたい経験」の2つのみを答える人が多いのですが、それだと正しく解答できていないと判断されてしまいます。
問われていることに線を引くなどして、何を答えるべきなのかしっかり確認した上で書き始めましょう。
⑤問題文の主旨からズレている
問題文の主旨に合致した論文を書くことは当たり間ではあるものの、意外とズレてしまうことがあります。
例えばなんとなく書き始めたり、事前に整理せずに考えながら書いてしまうと文章構成がぐちゃぐちゃになり、問題の主旨から大きく外れてしまうことがあります。
仮に字数や誤字脱字等の基準を満たしていたとしても、主旨と異なることを書いてしまえば点数をつけてもらえないかもしれません。
そうならないためにも、書き始める前に構成をしっかり考えた上でどのように論証していくのか、ゴールを見据えて書き進めていく必要があります。
自分が何を書くべきなのか、メモや頭の中で整理してから書き進めていきましょう。
まとめ
今回は、足切りになる割合や原因についてお伝えしました。
ご紹介した通り、しっかりとポイントを押さえて書けば、基本的に足切りに引っかかることはありません。
ただし一定程度の完成度は必要になるため、無対策で臨むことのないよう注意して取り組んでいきましょう。
ちなみに、下記の記事では公務員試験の論文模範解答例を多数紹介しているので、ぜひ併せて参考にしてください。