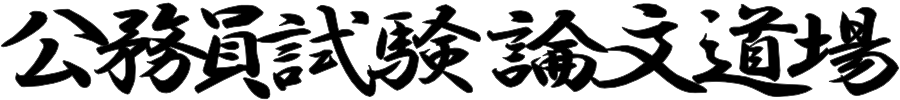現在、公務員を目指す方の多くは、試験対策に奮闘しているかと思います。
そんな公務員試験の中でも、特に対策が難しいと思われがちなのが「論文」。
今回は、論文試験の頻出テーマである「環境問題」にスポットを当てて、効果的な対策を詳しくご紹介していきます。
合格者答案も模範解答として載せているので、今まさに公務員試験対策をしている方にとって非常に参考になると思います。
「環境問題」をテーマにするにあたり、押さえておくべきコツは主に次の3点です。
・環境問題を解決するための「4R」
・構成の「型」を押さえる
それぞれ詳しくご紹介していきます。
あわせて、下記の記事では公務員試験の論文頻出テーマをまとめたものを紹介しているので、まだ読んでいない人はこちらも読んでみてください。
環境問題に関する3つのポイント

我々の経済は「大量生産・大量消費」によって発展してきましたが、それによって大量のごみが排出されるようになりました。
こうした背景や「SDGs」などに見られるように、近年は特に環境問題について注目されることが多く、論文でも頻出テーマの一つとなっています。
環境問題について論ずる前に、まずは次の3つのポイントを押さえておきましょう。
①プラスチックごみの増加による環境汚染の拡大
②有限の資源やエネルギーの浪費
③ごみ処理をめぐる都市部と地方の対立
それぞれ詳しく見ていきます。
①プラスチックごみの増加による環境汚染の拡大
ごみ問題の1つ目のポイントは、プラスチックごみの増加による環境汚染の拡大です。
昔は、ごみの種類は生ごみや紙などの可燃性ごみが比較的多かったのですが、年代が進むにつれてそれらはプラスチックへと変化していきました。
現在ではごみの総排出量のうち約4割がプラスチックごみであると言われています。
プラスチックごみの問題点は、処理をする際に有毒ガスが発生し、大気汚染の原因となる物質が排出されてしまう点にあります。
またプラスチックが風やポイ捨て等により海に流れ着くと、海洋生物にも悪影響を及ぼします。
今や海洋ごみの6割以上はプラスチックが占めているのです。
さらに、海に流れ着いたプラスチックは波に打たれたり、紫外線にさらされたりすることで小さく砕けていき、最終的には「マイクロプラスチック」と呼ばれる粒子になります。
このマイクロプラスチックは、砕けていく過程で表面に海中の汚染物質が吸着します。
それを海洋生物たちが食べてしまい死んでしまう事例が後を絶ちません。
そして最終的には、そうした海に生息する魚を食べる私たち自身にも被害が拡大することに繋がっていきます。
②有限の資源やエネルギーの浪費
2つ目のポイントは、有限の資源やエネルギーの浪費です。
大量生産・大量消費する社会は資源をたくさん使いますが、私たちがモノを生産する過程で消費する化石燃料や森林、海洋資源などは無限ではありません。
現代を生きる私たちには、地球の資源が枯渇してしまわないよう、この限りある資源を無駄にしない社会をつくることが求められているのです。
例えば資本主義社会の日本にあっては、利益を追求することは当たり前です。
しかし多くの企業や事業者が利益を追及してしまうばかりに、需要と供給バランスが崩れてしまい、資源やエネルギーの無駄づかいが発生してしまっていることも確かでしょう。
これからは大量生産・大量消費を見直し、有限の資源やエネルギーを効率よく使い、ごみを減らすことを目指していくことが必要です。
最近では「食品ロス」も問題視されており、大きな社会問題として注目されています。
そのため、公務員試験対策では「消費→循環」への方針転換に関して知識を深めていくことが大切です。
③ごみ処理をめぐる都市部と地方の対立
3つ目のポイントは、ごみ処理をめぐる都市部と地方の対立です。
一般的に都市部のごみは地方で処理される形となっているため、都市部の住民たちからは地方の被害は見えづらい構造になっています。
都市部でよくある意見としては「ごみ処理場は費用が抑えられる地方につくるのが経済的である」というものです。
しかし、地方から見ればこの意見はどうでしょうか。
「他人が出したごみを自分の家で処理するなんておかしい」と思うのは当然かもしれません。
このような対立から、自治体間でトラブルにまで発展するほど都市部と地方の利害の不一致が問題になっています。
環境問題を解決するための「4R」
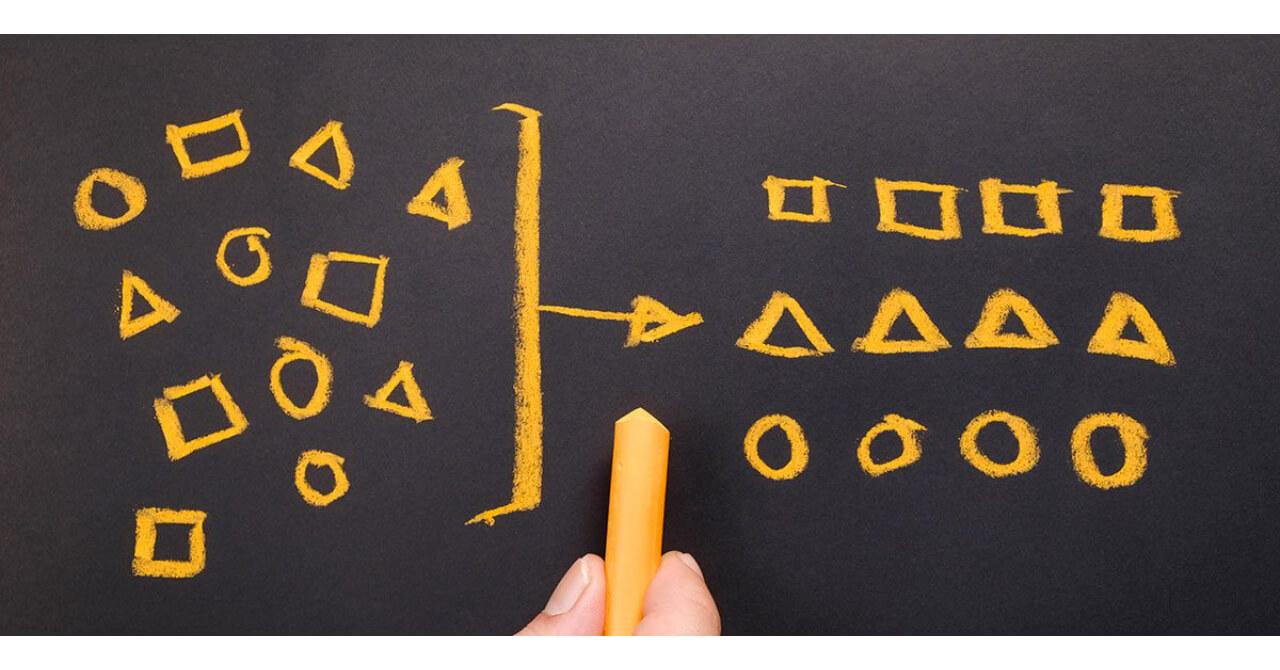
環境問題は自治体間の衝突もあることから、すぐに解決しにくいとされています。
しかし以下の3つのポイントに着目しながら「4R」について考えていくことで、解決の糸口が見つかりやすくなります。
→Refuse(リフューズ)、Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル)の略・リフューズ:ごみになりそうなものを拒否することで、ごみの発生そのものを抑えること
・リデュース:できる限り発生するごみを減らすこと
・リユース:使わなくなったものを繰り返し使うこと
・リサイクル:製品を資源やエネルギーとして再利用すること
①企業の取組
②個人の取組
①企業の取組
4Rのうち企業ができる取組としては「リデュース」「リユース」「リサイクル」の3つがあります。
具体的なリサイクル事例としては例えば、
・ビール瓶などを殺菌してもう一度使う(リユース)
・回収した製品に適切な処理を施し再利用する(リサイクル)
などが挙げられるでしょう。
有力企業が高度な技術とコストパフォーマンスを活かすことで、ごみの削減に貢献することができます。
しかしこうした技術はコストもかかり、簡単に行えるものではありません(今回のリユース例は例外かもしれませんが)。
そのため4Rを推進していくためには、自治体の事情を一方的に押し付けるのではなく、企業側にもメリットがある形で協働施策を推進していくことが求められます。
②個人の取組
個人ができる取組としては、主に「リフューズ」「リデュース」「リユース」の3つがあります。
具体的なリサイクル事例としては例えば、
・食料品は食べきれる量を購入しまとめを買いしない(リデュース)
・身の回りにあるものは修理して長く使う(リユース)
などが挙げられるでしょう。
また「リサイクル」についても、個人がリサイクルそのものを行うことはできませんが、その一助として缶・びん・ペットボトルや紙類など、ごみの分別をしっかり行うことは有効であると考えられます。
こうした取組は個々人に委ねられている部分が大きいため、身近なところから意識を変えていくことが必要です。
個人単位での意識改革をするためには、例えば自治体が企業や学校と連携するなどして、取組を推進していくことが重要と言えます。
【具体例で紹介】構成の「型」を押さえよう!
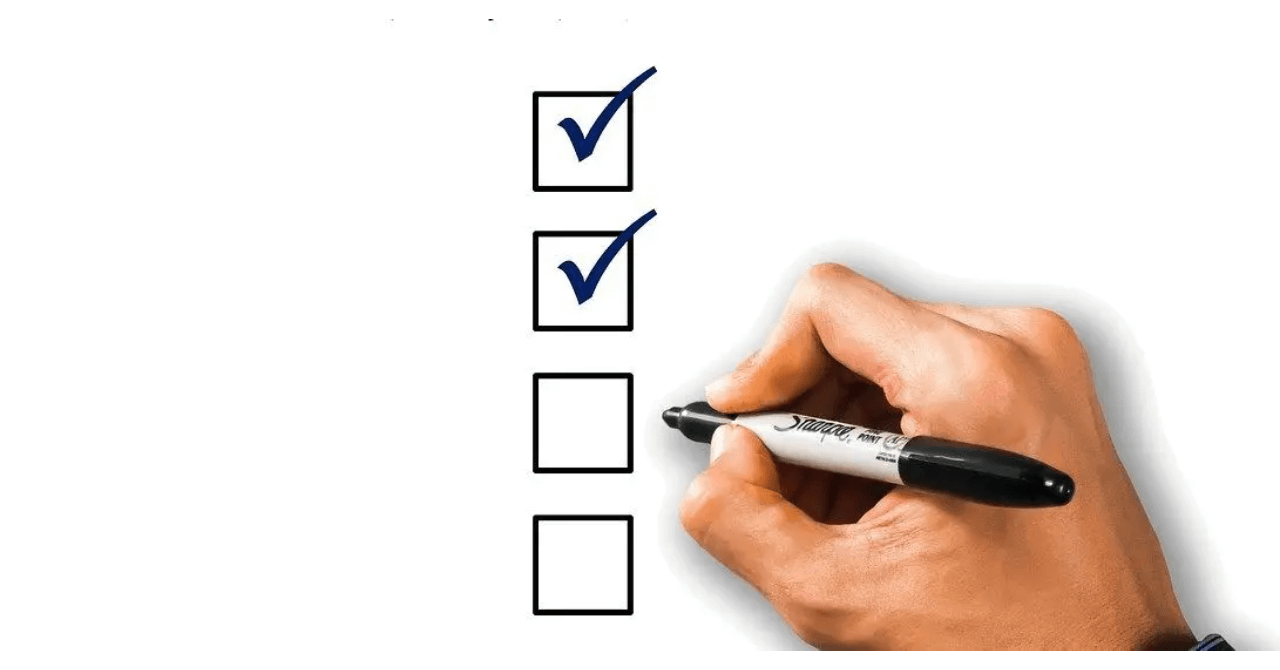
環境問題のポイントや4Rを押さえたら、いよいよ記述の練習です。
論文が苦手な人はいきなり書き出してはいけません。
まずは論文構成の「型」をしっかり頭に入れましょう。
①問われたことについての自分の意見
②現状分析とその問題点
③解決策や取組
④解決策や取組の根拠
⑤結論
続いて広島市の過去問を例に、この型をどう使うか具体的に見ていきます。
【2019年】
広島市におけるごみ排出量は、平成13年度以降減少傾向にあったが、平成23年度からおおむね横ばいの状況にあることから、本市はリサイクルの推進や食品ロスの削減等に取り組んでいる。こうした状況の背景を考察した上で、本市としてごみの減量化を推進するためにどのような取組を行うことが有効か、あなたの意見を述べよ。<広島市役所>論文過去問を参照
・企業との協働や市民への啓発により、ごみの減量化を実現する。
・広島市では、ごみの減量化への取組としてすでに〇〇や〇〇などが行われているが、それだけでは十分とは言えない。資源・エネルギー無駄づかいや減量化の鈍化は大きな課題である。
・循環型社会の構築として「4R」を推進していく。そのために、市民への啓発活動や教育機関との連携を強化する。
・持続可能エネルギーの開発やリサイクル産業の育成を図るため、費用面での助成を行う。
・「4R」をはじめとした循環型社会を推進していくことで、ごみの量そのものの減少や省エネルギーへの貢献が可能となる。
・企業側のハードルとされるコスト面をサポートすることで、リサイクル産業の活性化へと導くことが可能となる。
①で述べた自分の考えを、②~④を踏まえて結論として再提示する。
いかがでしょうか。
上記の①~⑤の構成の型は、基本的にどのようなタイプの論文にも応用することができます。
また、設問文の中に「具体的に挙げて…」などの文言があった場合は、「③解決策や取組」の部分には「自分ならこういう経験・能力を活かして、このように取り組む」という“自己のスキルアピール”をさらっと入れましょう。
今回の広島市の過去問のように自己PRを直接的には求めていない場合、それをくどくどと書くのは逆効果になるので注意が必要ですが、課されたテーマの流れの中での自然なアピールは可能な範囲で入れておきたいところです。
なお、このようなテーマが出題された場合には、ごみ問題についてある程度情報を押さえていないと記述ができないため、日常的に県庁や市役所の公式サイトをチェックし、最新情報をインプットしておきましょう。
【合格者答案】論文模範解答例

ここで、参考までに合格者の論文模範解答を掲載しておきます。
全文を読み、「こういう風に書けばいいんだ」という感覚を掴んでみてください。
【環境問題】模範解答例
日本はパリ協定により、2030年までに温室効果ガスの排出量を2013年度に比べ26%削減する目標を掲げている。○○県としても、温室効果ガス削減に力を入れて取り組むべきだ。現在の状況を放置すると、温室効果ガスの悪影響として、昨今深刻化しているゲリラ豪雨による被害や、運動が原則禁止になるほどの日中帯の気温上昇をさらに拡大させる危険性も高い。こういった被害を未然に防ぐために行政は、住民、事業者と協力して課題に取り組むことが急務である。
具体的には、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出が少ない「低炭素社会」の実現に向けて対策を講じなければならない。福島第一原子力発電所の事故以降、電力源として火力発電への依存度が高まっており、現状のままでは二酸化炭素排出量削減は難しい。そこで行政には、住民、事業者に対し、二酸化炭素排出量の削減に向けた行動をとるよう促す施策が求められる。施策の対象を住民と事業者それぞれに分けて、以下に論じる。
第1に、事業者に対して、補助金交付を強化していく。特に省エネ施策の導入が費用面から難しい中小企業への補助金交付が必要である。また、事業者が実施する省エネや環境配慮への取組については、事業者の利益に繋がるような仕組みを整えていくことも重要だ。具体的には、省エネに積極的に取り組んでいる事業者に対し、行政による表彰や認定を行う。これにより、事業者にとっては社会的信頼性の向上や企業イメージの向上に繋がりつつ、温室効果ガスの削減も推進していくことが可能となる。これは、企業のCSRの観点からも有効な施策であると考える。
第2に、住民に対して、自分たちの暮らしがどれだけ環境へ負荷をかけているかを認識してもらえるような施策を行う。ある自治体では、電気、ガス、水道の使用量を統計にとり、それらの二酸化炭素排出量を計算するという「環境家計簿」の取組を行った。これによって住民は、自分たちが排出する二酸化炭素の量をより意識するようになった。住民の無駄なエネルギー消費を控える意識づけに成功した事例である。○○県ではこの施策を参考に、さらに以下の提案をしたい。日常的に行える二酸化炭素削減の方法を提示して数値化し、県民に広く知らせていくのである。具体的には、移動に自家用車ではなく公共交通機関を利用する場合、二酸化炭素をどの程度削減可能であるかなどを載せたリーフレットを制作し、県民に配布する。加えて、二酸化炭素削減の行動により、家計がいかに節約できるかも数値を例示してリーフレットに掲載することで、県民の意識向上と自発的な行動を促せると考える。
前述のように地球温暖化対策は○○県としての課題だけではなく、日本全体の課題である。よって○○県は住民や事業者に対して二酸化炭素削減を促し、それに効果的に取り組むための方針を示し、低炭素社会を実現しなければならない。そして、○○県は日本で最も先進的に二酸化炭素削減に取り組むモデル県となることを目指し、さまざまな取組に努めるべきであると考える。
【特別区専用】論文模範解答例を無料公開!
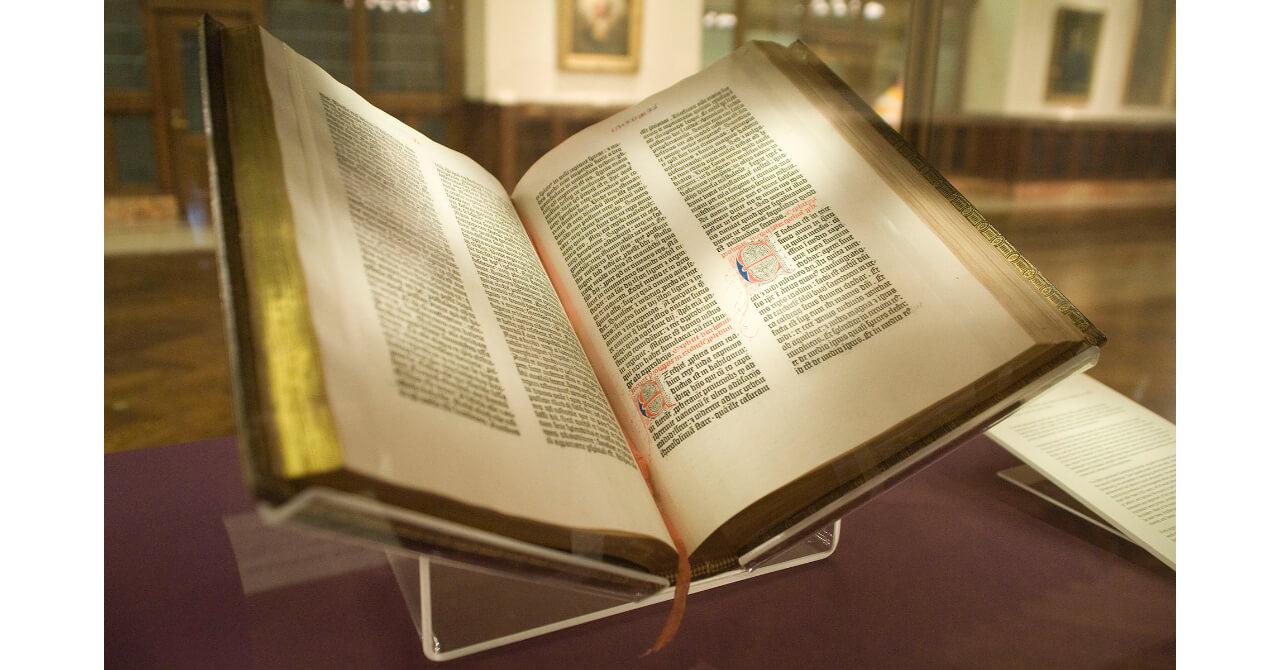
環境問題はどの自治体でも出題可能性が高い頻出テーマですが、特に論文の重要性が高い特別区においてもやはり過去に出題があります。
そこで受験生の皆さんに参考にしていただくために、下記の記事では公務員試験論文道場で指導を受けた特別区Ⅰ類合格者の模範解答例を無料公開しています。
テーマ別に掲載しており、環境問題(循環型社会)についても公開中です。
特別区を受験しない人でも十分、論文対策の参考になるので一読して損はありません。
【裁判所専用】論文模範解答例を無料公開!

環境問題は国家公務員試験の頻出のテーマとしても知られており、裁判所での出題が確認されています。
そこで受験生の皆さんに参考にしていただくために、下記の記事では公務員試験論文道場で指導を受けた裁判所一般職合格者の模範回答例を無料公開しています。
テーマ別に掲載しており環境問題(地球温暖化)についても公開中ですが、裁判所を受験しない人でも参考になること間違いなしです。
まとめ
今回は、公務員試験の論文の頻出テーマである「環境問題」について解説しました。
最後に環境問題のテーマで事前に押さえておくべきポイントを2点まとめておきます。
・自治体の「リサイクル推進」や「食品ロス」に関して情報収集をしておく
まずはこの2点を柱にして情報収集し、実際に書いてみてください。
こうした情報をもとに論文を書いていくと、行政や志望先が抱えている課題にマッチした内容になりやすくなります。
なお、下記の記事では全国の公務員試験の論文過去問をまとめています。
公務員試験受験生は参考にしてみてください。