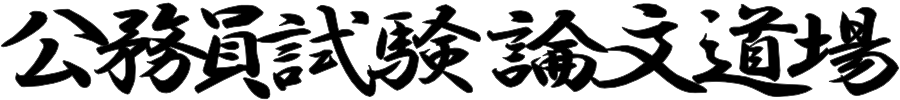現在、公務員を目指す方の多くは、試験対策に奮闘しているかと思います。
そんな公務員試験の中でも、特に対策が難しいと思われがちなのが「論文」。
今回は、論文試験の頻出テーマである「人口減少(少子化)問題」にスポットを当てて、効果的な対策を詳しくご紹介していきます。
合格者答案も模範解答として載せているので、今まさに公務員試験対策をしている方にとって非常に参考になると思います。
「人口減少(少子化)」をテーマにするにあたり、押さえておくべきコツは主に次の3点です。
・効果的と思われる少子化対策の整理
・構成の「型」を押さえる
それぞれ詳しくご紹介していきます。
あわせて、下記の記事では公務員試験の論文頻出テーマをまとめたものを紹介しているので、まだ読んでいない人はこちらも読んでみてください。
少子化問題で押さえるべきポイント
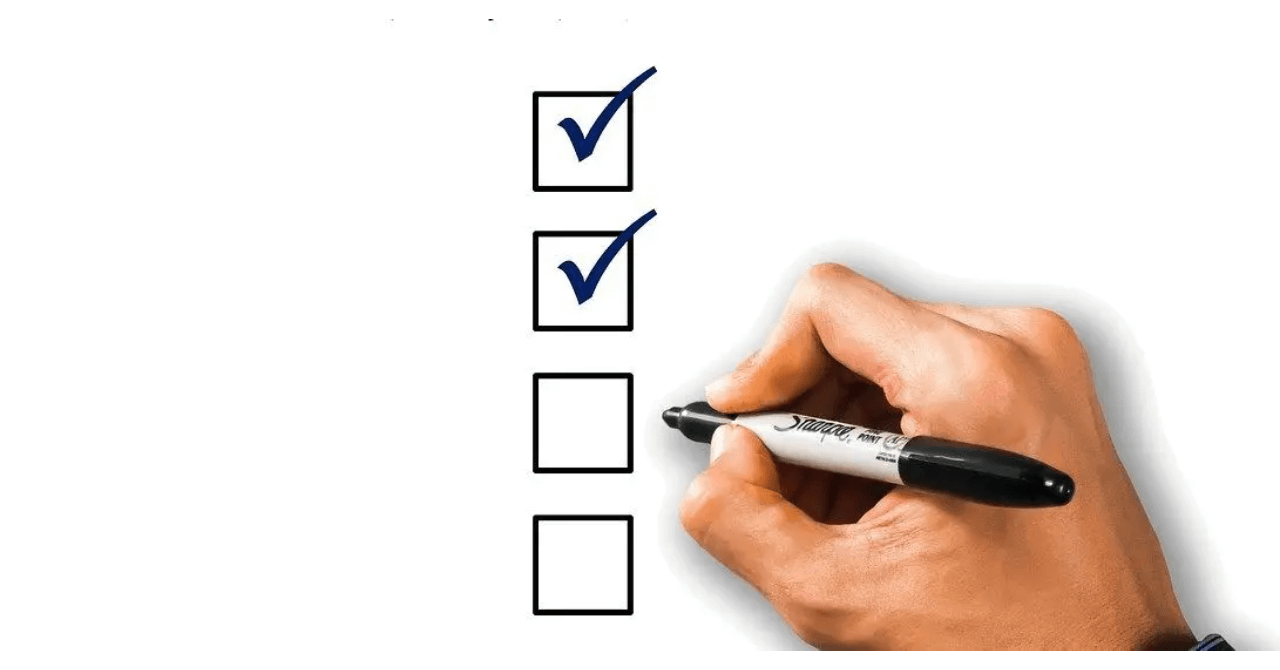
少子化問題とは、出生数の減少にともない人口減少に繋がっている問題のことです。
1970年代に第2次ベビーブームが到来した日本。
本来なら2000年代に入る時期に、第2次ベビーブームの時に産まれた子どもたちが結婚・出産をし、人口は増えていくはずでした。
ところが出生数は減少の一途を辿り、人口減少へと繋がってしまいました。
少子化問題で押さえるべきポイントはたくさんありますが、今回は公務員試験の論文対策で特に必要な視点を2つ紹介します。
①女性の晩婚化
1つ目は、女性の晩婚化です。
戦後は女性の社会的地位が上昇したことで、家庭だけではなく仕事でキャリアを形成する女性が増えていきました。
そうした女性が、結婚よりも仕事を選択することで必然的に晩婚化が進み、結果的に少子化問題に繋がる結果となったのです。
さらに、女性の社会進出に伴うサポートも不十分な環境です。
近年は自治体が託児所を設置したり、企業が男性の育休を推進したりするケースが増えてきてはいるものの、出産後の女性が職場復帰できるようなサポートや体制はまだまだ伸びしろがあります。
女性としては出産後に十分働けるような環境が整っていないということから、結婚や出産を諦める、もしくは遅くなってしまい、結果的に未婚や晩婚化が増えて少子化問題に拍車をかけている状況です。
②出産後の母親の負担増
2つ目のポイントは、出産後に母親の負担が増えることです。
女性の社会進出や働く女性へのサポートが不十分な点も少子化問題に繋がる課題ですが、女性の育児負担が大きいことも問題視されています。
基本的に、育児は父親が協力的でなければ母親がすべて行うことになります。
このような悪循環となり、結果的に少子化問題へと繋がっているのが日本の現状です。
【論文で使える】効果的な少子化対策とは?
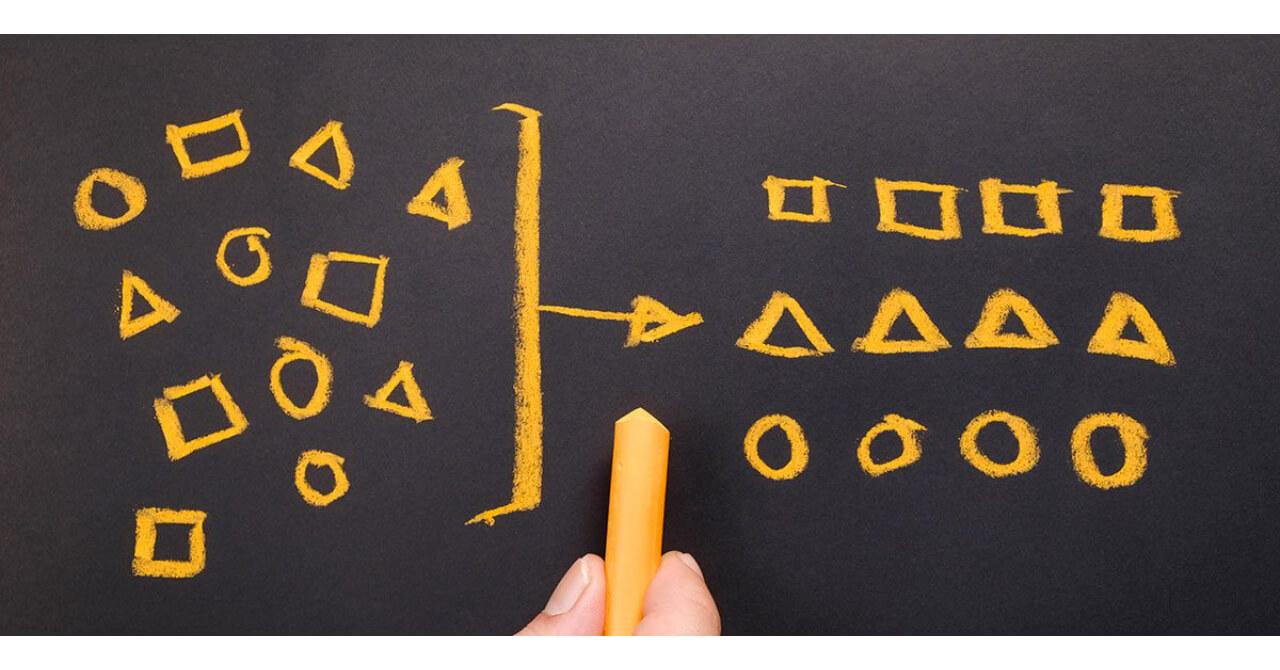
少子化問題のポイントをまとめると、女性の晩婚化と出産後の女性の負担増ということでした。
これらを解決するために考えられる対策としては、「育児環境の整備」「労働環境の整備」の2点が考えられます。
育児環境の整備
まず夫婦で協力して育児をするためには、父親・母親の双方がバランスを考えて育児を分担していく必要があります。
これについては各家庭の事情によって異なる部分があるものの、行政は男性の育児参加を推進する取組を実施しています。
また育児をするためには、保育所整備や補助金などの子育て支援も欠かせません。
特に近年は核家族化に伴い、祖父母や親戚など近しい人からの協力を得られにくい環境となっています。
行政側は必要な法律や制度があれば積極的に話し合い、財政的な根拠を明確にしたうえで手厚いサポートをしていく必要があるでしょう。
労働環境の整備
そして労働環境を整えるためには、夫婦というより企業側に求められる努力です。
例えば男性の育休は未だ取得しにくい風潮が残っており、各企業は上司から部下に育児休暇を取得するよう促すなど、取得しやすい雰囲気を整えていく必要があります。
時短勤務等についても、男女問わず適切に利用できるよう促していく必要があるでしょう。
近年は男性の産休等も増えてきており、育児負担の軽減に向けて企業も様々な取組を実施しているところです。
こうした取組を加速度的に推進するためには、企業と連携して行政もサポートしていく姿勢が求められます。
近年の新しい取組
さらに近年注目されている少子化対策の事業として、各自治体が行っている移住促進事業というものがあります。
これは人口が減っている地方への移住を促進するための取組ですが、こういった取組も少子化問題への対策として有効と考えられています。
そのため論文で少子化問題のテーマが出題された際には、移住促進事業の視点から論じてみるのも良いでしょう。
地方移住は地方の人口を増やすことで働き手が増え、活気が出ることで地方創生にも繋げることができます。
メリットも多く注目されている取組なので、チェックしておいて損はありません。
【具体例で紹介】構成の「型」を押さえよう!

少子化対策を整理したら、いよいよ実際に書く練習に入りましょう。
論文が苦手な人はいきなり書き出してはいけません。
まずは論文構成の「型」をしっかり頭に入れましょう。
①問われたことについての自分の意見
②現状分析とその問題点
③解決策や取組
④解決策や取組の根拠
⑤結論
続いて青森県庁の過去問を例に、この型をどう使うか具体的に見ていきます。
【2019年】
人口減少し、超高齢化時代を迎える青森県が今後も地域として生き残るために、今、特に力を入れて取り組むべきことについて、あなたの考えを述べなさい。<青森県庁>論文過去問を参照
・「地域における少子化対策」を一層推し進めていく。
・出生率が低水準で長期間減少傾向にあること。
・保育所を整備し、子育てしやすい環境を整える。
・住宅費などを補助し、家庭生活をサポートする。
・ひとり親家庭の支援や子育てにやさしい企業認定制度を推し進める。
・人口減少は少子化が進んだ結果なので、複数の対策を長期的に行うことが不可欠。
・教育や保育に携わる人材の育成や確保を継続的に実施する。また、待遇や労働環境も整備して長期間の雇用に繋げていく。
①で述べた自分の考えを、②~④を踏まえて結論として再提示する。
いかがでしょうか。
上記の①~⑤の構成の型は、基本的にどのようなタイプの論文にも応用することができます。
また問題の中に「今、特に力を入れて取り組むべきことについて…」という部分がありますが、こういった場合は次の型を押さえておくと論述しやすくなります。
ポイントは、各自治体の課題を分析しつつその内容を踏まえた提案をすること。
各自治体が抱えている課題は自治体のHPなどで確認できますから、事前に情報収集しておきましょう。
そして情報収集の際、特に押さえておくべきトピックは次の通りです。
・ひとり親支援
・若者の出会いや結婚支援
これらはノートなどにまとめて、すぐに見返せるようにしておくとベストです。
公務員試験の論文対策は難しいように思われますが、大切なのは日頃から自治体の情報をチェックしてアップデートすることです。
情報を得たのが半年前…となると、公務員試験のときにはその情報が古くなっている可能性があるので、こまめなチェックを心がけていきましょう。
【合格者答案】論文模範解答例
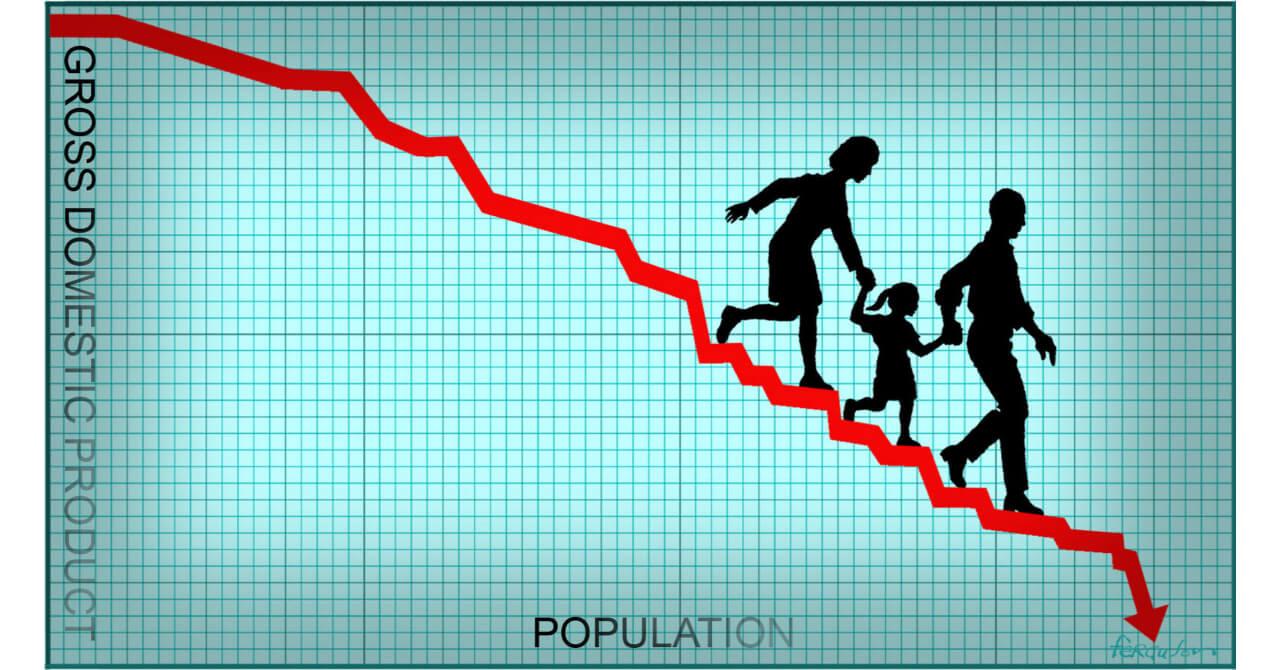
ここで、参考までに合格者の論文模範解答を掲載しておきます。
全文を読み、「こういう風に書けばいいんだ」という感覚を掴んでみてください。
【少子化問題】模範解答例
日本の少子化が進行する背景には、経済的に余裕がなく結婚や出産をしない若年層が多いことや、働く女性の増加、また結婚や出産に対する価値観の変化といったさまざまな要因があり、それが未婚化や晩婚化に拍車をかけている。未婚化や晩婚化の進行に伴って、日本の合計特殊出生率も低下し続けており、現在は1.34%と、政府目標である1.8%を大きく下回っている。
このまま少子化が進行してしまうと、生産年齢人口はますます減少するだろう。すると日本及び○○県の経済力は下降の一途をたどってしまう。そこで○○県は、少子化を少しでもスローダウンさせる策を講じるべきである。具体的には次のような3つの取組を行うべきだと考える。
第1に、若年層が結婚できるようになる取組の推進である。若年層が結婚しない背景として、結婚したいという気持ちは持っているが、非正規雇用であるために、結婚するために必要な収入を得られていないという人たちが多く存在するという現実がある。この問題に対しては、正規雇用率を上昇させる取組や、フリーターに対する職業訓練などを行政は積極的に行うべきである。また、そもそも結婚する相手に出会う機会が少ないために、未婚化や晩婚化が進んでいるという側面もあるため、無料の結婚相談所の設置やオンラインを活用した婚活イベントを行政が主催することも有効である。
第2に、出産しやすい環境づくりである。内閣府の調査では、夫婦が子供をもたない理由の第1位が、「子育てや教育に費用がかかるから」であるとの結果が出ている。そのため行政は、経済的な支援制度を拡充し、この問題の解消に努めるべきだろう。具体的には、不妊治療費の一部助成や新婚の祝い金制度の拡充である。
第3に、子育てしやすい環境づくりである。多くの働く女性が、仕事と家事の両方に加え、さらに子育てもするとなると負担が大きいため、出産に対する不安を持ったり、出産を敬遠したりする気持ちを抱いている。この課題の対策としては、子どもの一時預かり所の施設を増設したり、預かり時間帯を増やしたりすることで、育児の負担を軽減できるだろう。また、各事業所に男性が育児休暇を取りやすい環境を作るように促し、夫婦が協力して子育てできる体制を整えることも、子育てへの不安の軽減に貢献するだろう。また、地域全体で子育てすることも効果的だ。すなわち、住民の協力を得て若い夫婦の子育てを支援していく。具体的には、高齢者や子育ての先輩が子育てを手伝うマッチングシステムを整備したり、地域ボランティアの協力を得て子育て相談会を開催したりするなど、地域コミュニティで子育てをサポートしていく体制を行政が整えることが考えられる。
以上の対策を講じることで若年層の結婚や出産を支援し、○○県の少子化の進行に歯止めをかけることが必要だと考える。
まとめ
少子化問題を適切に論ずるためには、現状の把握が必要不可欠です。
そのために情報収集が必要ですが、まずは下記のような取組を調べてみるのがおすすめです。
・企業の育児休業制度
・ひとり親支援
・若者の出会いや結婚支援
これらを中心に情報収集をしていき、実際に書いてみてください。
そうしてできた答案を第三者に読んでもらい、ブラッシュアップを重ねていくことが論文上達に繋がります。
ぜひご紹介した記事内容を公務員試験の論文対策に役立ててください。
なお、下記の記事では全国の公務員試験の論文過去問をまとめています。
公務員試験受験生は参考にしてみてください。