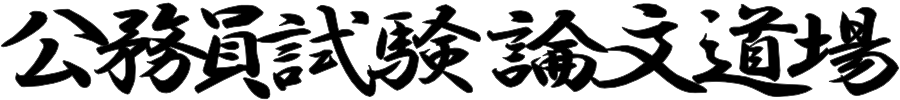と悩んでいる人が少なくないと思います。
論文対策は「○か月に前に始める」などのルールはありませんが、想像以上に時間がかかるため、早めに取り掛かるに越したことはありません。
それに、志望先によっては教養対策や面接対策などもあるため、論文対策だけに専念できるわけではないというのも注意すべき点です。
そこで今回は、論文対策をスタートするべきタイミング、そして早めに対策を始めるべき理由などについて解説していきます。
本記事で分かることは次の通りです。
・論文対策を早めに始めるべき4つの理由
・論文対策の流れ
・論文対策を始める時期
ちなみに、下記の記事では公務員試験の論文頻出テーマをまとめています。
全国の市役所・県庁の出題傾向を徹底的に分析しているので、ぜひ併せて読んでみてください。
公務員試験の論文ってどういう形式?

試験対策を進める上では、そもそも試験内容がどういうものなのかについて把握しておかなくてはなりません。
試験内容が分からないと、逆算してスケジュールを立てることができないからですね。
しかし県庁や市役所、国家公務員でも全て同じ試験というわけではなく、組織や自治体によって出題内容は異なります。
そこでここでは参考として、多くの公務員試験で実施される形式をご紹介します。
・試験時間:1時間~1時間半
・文字数:600~1200字程度
内容は福祉、教育、環境、防災など多岐にわたり、課題の把握とそれに対する解決策を求められることが多いです。
また、規模の小さい市役所では自分の考えや思いを書くタイプの「作文形式」が多く、難易度としては行政課題形式よりも低くなります。
作文形式では、例えば「あなたの理想の公務員」というような大まかなテーマが出題されます。
これらに加えて学生だと「自己PR型論文」、社会人採用試験だと「職務経験論文」という形式の場合もあり、受験する組織に合わせた対策が求められます。
文字数については、「なんだ、何千文字も書くわけではないのか」と感じたかもしれませんが、文字数が多くないからといって簡単というわけではないのが公務員試験の難しいところです。
極端にいえば、たとえ100字であっても勉強しておかなければ「合格できる文章」は書けません。
特に地方公務員試験では論文の配点が高いことが多いため、しっかり対策をしないと合格することは難しいです。
論文対策を早めに始めるべき4つの理由
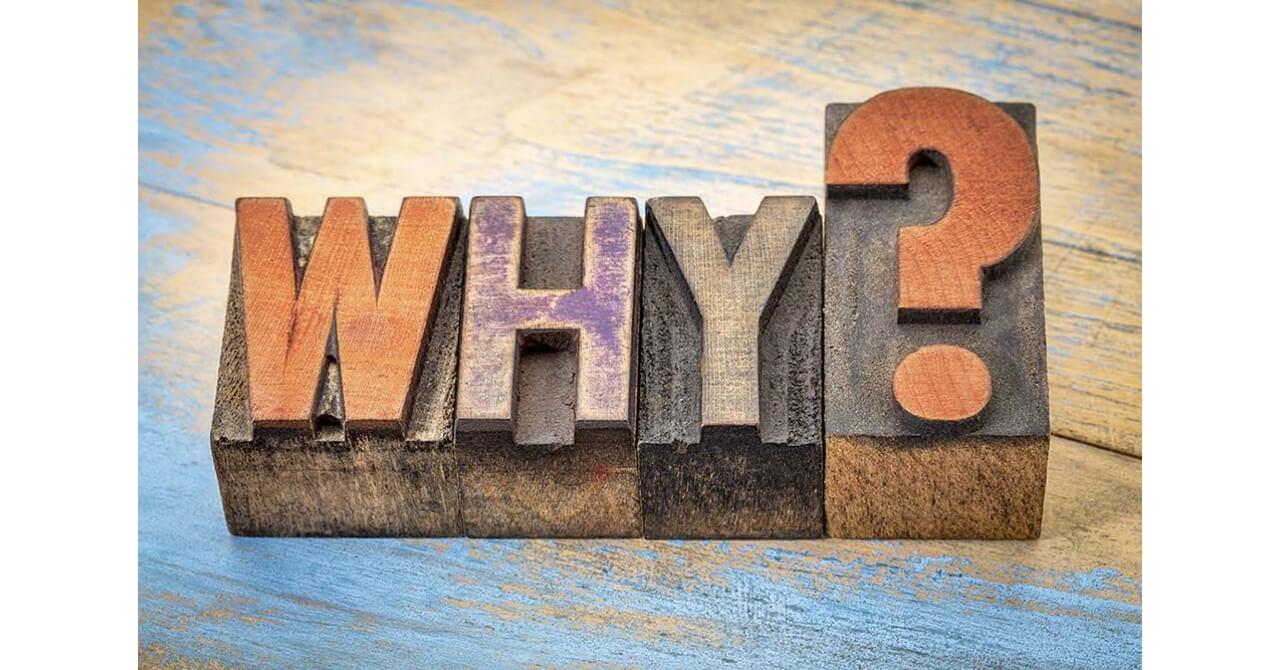
出題形式が分かったところで、本題である実際に対策を始める時期について解説していきます。
結論から言うと、論文対策は教養試験対策と同じタイミングでスタートすることをおすすめします。
ただし、教養試験対策は毎日一定時間勉強することが推奨されるものの、論文試験は必ずしもその必要はありません。
「必要はない」どころか、毎日時間を費やしてしまうと他の勉強に支障をきたすことになる可能性があるため、数日おきに書く練習を入れるなどバランスを考えて取り組んでいくことが大切な科目です。
ということでここからは、早めに論文対策をスタートするべき理由を4つ挙げていきます。
①情報収集をしなくてはならない
先に説明した通り、論文試験の出題形式は受験先によってバラバラです。
例えば出題形式によっては、2題から1題を選択して解答するものもあれば、提示された1題だけに解答するものがあります。
その他にも問題文が文字だけのものもあれば、表などのデータが記載されていてそこから読み取れることを書かせる形式などもあり、受験先によって傾向がかなり変わってきます。
こうしたことから、論文対策では受験先に合わせて情報収集をしていかなくてはなりません。
さらに、受験先の頻出テーマを押さえる必要もあります。
特に行政課題形式の試験では過去問と似たような問題が出題されることも多く、どのようなテーマが出題されたのかを把握しておくことは必須です。
そして論文でしっかり得点していくためには、少なくとも20テーマ程度は扱える(自在に論文へと落とし込める)ようになっておきたいので、準備する時間をしっかり確保するという意味でも早めに取り組むことが重要となります。
ちなみに論文テーマについては、下記の記事で公務員試験の論文頻出テーマをまとめたものを紹介しています。
行政課題に関するテーマを扱っているので、論文対策にぜひ活用してください。
②添削してもらわなければならない
論文対策においては、自分が書いた論文を添削してもらうことが必須です。
なぜならチェックを受けずにいくつも論文を書いても、それが正しい書き方なのか、主張している内容は間違っていないか等、自分で判断することは困難だからです。
しかし添削にはそれなりの日数がかかりますし、論文が返却された後は修正作業(指摘を受けた箇所を正しい文章に書き直す作業)もしなくてはなりません。
このように論文では「一つ論文を書く→添削を受ける→修正する」という一連の工程があるため、かなりの時間を消費すると考えておきましょう。
③論文対策だけに専念できるわけではない
仮に論文対策だけに専念できるのであれば、3か月程度の期間があれば十分かもしれません。
要領の良い人であったり、論文試験が簡単なものであったりすれば、1か月ほどでもなんとかなる可能性はあるでしょう。
しかし実際には、論文対策を進めながら教養試験など他の試験対策にも取り組まなければなりません。
また、特別区など専門試験が課される自治体であればここに専門試験対策も加わり、SPIが実施される組織であればSPI試験対策などもあるでしょう。
論文試験と面接試験の日程が近い場合には、面接試験対策も同時進行で必要です。
さらに併願している場合はどうでしょうか。
併願先の試験対策もあれば、第1志望先の論文対策だけに集中できる時間は限られてくるでしょう。
このように他の試験科目や試験日程などによってスケジュールは左右されるため、早めに論文対策をスタートして、余裕をもって準備しておく必要があるのです。
早く取り掛かれば取り掛かるだけ自分の苦手な部分も分かるようになるので、論文対策は後回しにしないようにしましょう。
④早めに始めておけば後から調整することもできる
早めに対策をスタートしておけば、自分で対策のペースを調整することができます。
例えば途中で「このペースで勉強しなくても間に合うな」と判断した場合には、勉強量を少なくすればよいでしょう。
反対に「遅く始めてしまい、間に合わなさそうになってきたから勉強量を多くする」というのでは、試験勉強はほぼ間違いなく破綻します。
焦ってしまうとスケジュールも乱れて、他の試験科目等にも悪影響が及んでしまうため、早めに着手して確実な準備を進めていきましょう。
論文対策の流れ

それでは、ここからは論文対策を進める際の流れを紹介します。
以下のように進行させていけば、余裕をもって、かつ他の対策の妨げになることなく対策に取り組むことができるでしょう。
①受験先の情報を集める
最初に必要なことは受験先の情報収集です。
例えば、
・どのような問題形式か?(短文・長文形式、時間、文字数など)
・配点比率はどうか?(論文の配点がとても高いなど)
特に問題形式や配点比率は合格するために最も重要な指標となるため、過去問や受験案内をよく確認して戦略を立てていきましょう。
なお過去問については、下記の記事で全国の公務員試験の論文過去問をまとめたものを紹介しています。
志望先の自治体をチェックし、論文対策にぜひ活用してください。
「とりあえず勉強を始めて、しばらく経ってから受験先の情報を調べる」というのはかなり勉強効率が悪いため、まずは受験先の情報を集めることを最優先に取り組んでください。
②時事対策をしておく
論文試験には「時事の影響が及びやすい」という特徴があります。
そのため、論文対策を進める上では社会問題に関する最低限の知識が必要です。
教養試験レベルの時事対策までは求められていませんが、現在の日本および世界の情勢や行政の抱える問題などは知識として持っておきたいところです。
またそうした知識をただ吸収するのではなく、「その問題をどうしたら解決できるか?」という視点も持つことで、日頃から課題に対して考えるクセを身に付けていく必要があります。
1日1回はニュースに触れる環境をつくり、社会問題に関する重要語句や情勢について「全く知らない」ということがないようにしましょう。
③文章校正や国語のルールについて把握する
論文を書く上で、「今さら文章校正や国語のルールを勉強する必要なんてない」と感じている方もいるかもしれません。
しかしこれまで多くの受験生を指導した経験から言えることは、大人であっても最低限整っている文章さえ書けない人が少なくないということです。
昨今のスマホ利用の影響も大きいかもしれませんが、意外なほどにまともな文章を書けない人が多いのです。
ですから今一度、文章の基本ルールなどをチェックしておくことが重要です。
論文の内容そのものが良かったとしても、文章構成が悪かったり、文章の初歩的なルールを守れていなかったりすると減点は免れません。
高得点の論文を書き上げるためにも、練習段階でしっかり確認しておきましょう。
ちなみに下記の記事では、公務員試験の論文の書き方について紹介しています。
論文の書き方に不安を覚えている方もそうでない方も、自分の書き方に問題はないか、チェックするためにぜひ活用してください。
④模範論文を参考に実際に書く
論文や作文に限りませんが、文章は書けば書くほど上達していくものです。
実は小説家やライターなどの文章のプロフェッショナルも、書きながら徐々に文章がうまくなっている事例が多いんですね。
勉強を始めた最初のうちは、なかなか対策が進まなくて困惑するかもしれませんが、それでもまずは書いていくことが大事です。
頻度として、最低でも1週間に1回は書いてみると良いでしょう。
その際、本番と同じような試験時間や環境で書くようにすると、時間配分の感覚なども少しずつ身に付いていきます。
なお、模範論文については当サイトで無料公開しています。
下記の記事では公務員試験の論文模範回答例を多数紹介しているので、論文対策にぜひ活用してください。
⑤添削を受ける
先ほどもお伝えしたところですが、論文を書き終えたら絶対に添削を受けるようにしましょう。
その際、添削はプロにお任せするのがポイントです。
ここでの「プロ」というのは、論文対策について専門的に指導している人物のことです。
例えば、予備校や大学の講師などがそれに当たります。
合格者のほとんどは、こうした第三者からの添削をきちんと受けて訓練を重ねています。
初めのうちは完成度の低い論文しか書くことができなくても、プロの指導を守って修正を重ねていけば、着実に合格ラインの論文を書けるようになっていきます。
受験生の中には、「自分で添削するから大丈夫」と思う人もいるかもしれません。
しかし、受験生自身に試験官が評価するポイントなどの知識はないでしょうし、自身の文章を客観的にチェックすることもまず難しいでしょうから、素直にプロを頼ることを強くおすすめします。
論文対策はいつから始めるべきか?

ここまでの内容を踏まえると、論文対策を早めに始めることの重要性については分かったものの、具体的にいつから対策を始めれば良いのか疑問に思った人も多いと思います。
ところがこの部分については、これまでに論文の学習経験があるか、もともと文章を書くのが得意か等の様々な要因によっても変わってくるため、一概には言えないというのが正直なところです。
そのため結論としては「人によって対策を始める時期は異なる」ということにはなるのですが、これでは答えになっていないことも確かです。
そこで最後に、勉強を開始する時期を決める判断材料となる2つのポイントを紹介し、これら2点を軸に論文対策をスタートさせる時期を決めていってほしいと思います。
①志望先の出題形式
まずは志望先の出題形式から判断する方法です。
具体例として、特別区Ⅰ類の採用試験を挙げてみましょう。
・形式:課題式論文
・試験時間:80分
・文字数:1000~1500字程度
・設問文が長い
・特別区固有の事情を把握しておく必要がある
・教養と専門よりも論文試験の配点が大きい
特別区Ⅰ類では、上記のような特徴があります。
このような出題形式の場合は難易度が高いため、かなり早めに勉強をスタートしておくべきと言えるでしょう。
具体的なポイントをまとめると、
・文字数が多い
・設問文が長い
・志望先の固有事情を把握する必要がある
・論文の配点が大きい
このいずれかに当てはまる場合には、半年くらい前には対策を始めるのがおすすめです。
反対に、下記のように試験の難易度が低い組織もあります。
・文字数:600字程度
・自分のことについて書く
こうした組織の場合、難易度としてはそこまで高くないため、2~3か月くらい前からでも十分間に合わせることができると思います。
②現時点での自分の能力
次に自分の能力から判断する方法です。
つまり、一定レベル以上の論文(文章)を書く能力がどの程度備わっているのかによって、論文対策を始める時期は変わります。
例えば論文を一切書いたことがなくても、もともと文章力がある人であれば、行政知識を補強するだけで十分戦えるレベルまで持っていくことができる場合があります。
その場合には、論文の基本から応用までを学ぶ期間が人よりも少なく済み、トータルで論文対策に充てる時間がそこまでかからないということになるでしょう。
反対に文章を書くのがてんで苦手な場合には、半年以上などかなりの期間の練習が必要と言えます。
現時点での自分の能力を知るためには、一度、過去に出題されたテーマについて、何も見ずにまずは自分で書いてみるという方法がおすすめです(もちろん制限時間も本番通りに設定します)。
そこで完成した文章をプロに見てもらえば、「その時点における自分の論文の能力」が分かるはずです。
評価が芳しくない場合には、苦手であると判断し、早めに対策を始めていきましょう。
まとめ
教養や専門対策と比べると論文対策は後回しにされがちです。
中には「その場で何とか書けるだろう」と考えてほとんど対策をしない人もいますが、それでは合格は遠のいてしまいます。
近年、多くの受験生は論文対策にも力を入れてきているため、遅れをとらないためにもしっかりと準備していくことが大切です。
早めに教養試験等と同等に対策を行い、添削を受け、確実な合格へとつなげていきましょう。
ちなみに、下記の記事では公務員試験の論文模範解答例を多数紹介しているので、ぜひ併せて参考にしてください。